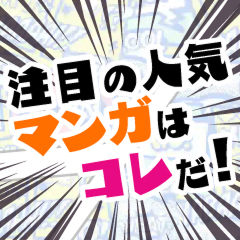「悪気がないからって許さなきゃいけないんですか?」子がいじめられる親の葛藤を描いた漫画『放置子の面倒を見るのは誰ですか?』。心理士でもある作者に話を聞いた
新小学1年生の娘を持つ主婦・しずかは、新生活への期待を胸に穏やかな日々を送っていた。そんなとき、入学説明会に1人で参加していた父子家庭の子「りっちゃん」が気になり、しずかは親切心からその子に手を差し伸べる。だが、「りっちゃん」は徐々に娘の莉華が嫌がることをするように…。「いじめっ子にも、優しくしなければいけないの?」子どもの友達に対する複雑な思いや葛藤、対応していく過程などを描いた漫画『放置子の面倒を見るのは誰ですか?』は、子育て世代から大きな共感を得ている。
今回は、そんな話題作の作者であり臨床心理士・公認心理師でもあるという、白目みさえさんに話を聞いた。



作者の白目みさえさんインタビュー
――漫画を描かれるようになったきっかけを教えてください。
幼いときから漫画を読むのが大好きでした。そのころから、漫画好きの少女なら誰もが抱く「漫画家になりたい」という淡い夢を抱きながら、中学生くらいまでは自分でもこっそり漫画を描いていた覚えがあります。しかし、年齢を重ねるにつれて夢は夢として胸にしまい、落書き程度に楽しむようになっていきました。
あらためて本格的に描き始めたのは、数年後に産休に入った漫画好きの同僚に、自分の落書きを見せたのがきっかけでした。同僚が初めての育児できっと荒んでいた時期に、クスッと笑えて、ひとときでも外の世界とつながり、「自分だけじゃないんだ」と思ってくれたらいいな、という思いで「うちの2歳は今日こんなことをしたよ」「今、うちは大惨事になってるよ」とくだらない日常の1コマをメモ帳に描き、LINEで送っていました。すると同僚から「これ、Instagramに載せてみたら?」と提案され、あくまでもその同僚や近しい友人にひと笑いを届けるつもりで始めたのが最初です。当時SNSに疎かった私は非公開アカウントにしておらず、全世界に発信してしまっていたことに気づいたのは、しばらく経ってからのことでした。結果的には、それでよかったのかもしれませんが…。
――「放置子」は近年、社会問題としても注目を浴びていますが、今作で「放置子」をテーマとして取り上げられた理由を教えてください。
私は田舎で育ちましたが、当時は「放置子」が今ほど目立たなかった気がします。「地域で育てる」というよりも、見守る大人すらいなくとも子どもたちだけで勝手に遊んでいました。そのため、いわゆる「放置子」という子もなかにはいたと思いますが、ある程度はほかの子どもたちに紛れていたのではないかと思います。
しかし、いざ自分が出産すると、ご時世がガラリと変化していました。小学生は集団登校が当たり前、子どもひとりで遠出はさせない、お友達同士で遊ぶときでも親同士で連絡を取り合う、GPSを持たせて帰る時間や今いる場所を確認する。そんなことが当たり前になっている中で、「放置子」は非常に目立つ存在となりました。
「放置子」という言葉がこれだけ注目されるようになったのは、ある意味、それが“特殊な存在”になってしまったからだと感じています。みんながある程度“適度に放置されていた”時代には、周囲の大人も子どもも、なんとなく対応できていましたが、今はそうではありません。社会全体で子育てのルールが細かくなったことで、ちょっと「普通」から外れた子が、とても目立つようになりました。だからこそ親も子も、どう接していいかわからず、結果的に「問題」として扱われてしまう、そんな現状があると思います。
ただし、親世代の人には「昔はこのくらいみんな関わってくれていたよな」という感覚もあると思います。「関わった方がいいのか」「いやでも今は関わらない方がいいのか」と戸惑いと葛藤を抱える方も多いのではないでしょうか。私自身もその1人でした。知識はアップデートされているのに、感覚だけが取り残されたようなモヤモヤがあります。だからこそ、「じゃあ、今の時代にできる関わり方ってなんだろう?」と考えたときに、無理に背負い込まず、専門家に託すという形もあっていいんじゃないかと思うようになりました。同じように感じている保護者に向けて、「専門家に託してもいい」という1つの選択肢をお届けしたくて、このテーマで作品を描くことを決めました。
――「放置子」という難しいテーマを扱っているので、漫画にする際に気を付けたり、工夫された点はありますか?
「放置子」というテーマはとても繊細で、背景も理由も1人ひとり違います。だからこそ、漫画として描くうえでまず意識したのは、「原因を決めつけないこと」でした。
作中でも母親のしずかが「愛着障害ってこと?」「発達障害ってこと?」と質問をして、心理士である白目が「わからない」と答えるシーンがあります。日常の会話の中でもよくあることだと思うのですが、なにか問題を発見すると、ついつい原因を特定したくなりますよね。なぜなら「原因」がわかると「対処法」もある程度用意されているからです。でも、その「原因」がそもそも間違っていたらどうでしょうか。たとえば「愛着障害」と「発達障害」では、接し方や支援のアプローチが全く変わってきますし、「愛着障害だけ」「発達障害だけ」と限定されることもほとんどありません。育ってきた環境、家族の事情、その子自身の気質…すべてが複雑に絡み合っていて、境界線もはっきりしないことがほとんどです。そうなると、「こうすればいい」という明確な答えは存在しないはずなのです。
さらに、「これが原因だ」と決めつけてしまうと、その子を「そういう子」として見てしまう危うさもあります。一度貼られたラベルは、周囲の大人たちにも、子ども自身にも伝わっていき、問題の本質を見誤ったまま解決を遅らせてしまうことすらあります。だからこそ作中では、あえて診断名や家庭環境の詳細な描写は避けました。読む人が「これ、あの子かも」「うちもこんなことあったな」と、現実の中で抱えている“違和感”や“もやもや”に、自分ごととして重ねられるようにしたいと思ったのです。明快な「正解」を示すことではなく、「正解が見えない状況の中で、それでも子どもとどう向き合うか」を、読んでくださる人と一緒に考えられるような作品を目指しました。
――ほかに、注力された点は?
本作では、「親がすべてをどうにかしなければ」と思い詰めてしまいがちな気持ちに対して、『少し距離をとって見つめ直すこと』の大切さを描きたいという思いがありました。苦しい状況に置かれると人はどうしても視野が狭くなり、「自分がなんとかしなきゃ」と抱え込んでしまいがちですが、周囲の人の存在や、小さな変化に目を向けることで、状況が少しずつ動き出すこともあります。そのような「見方の変化」や「関わり方の選択肢」を描くことを意識しました。「手を離す=無関心」ではありません。「すべてを背負わなくてもいい」という視点を持つことで初めて見えてくるものもあるのです。
最近の育児は、どうしても親だけが責任を負っているような空気になりがちですが、子どもを育てるのは本来1人ではできないことだと思います。「放置子」に悩む人も、自分の子どものことで悩む人も、誰かに「丸投げする」のではなく、「自分だけで頑張る」でもなく、「協力を得る」という選択肢があっていいと感じてもらえればと思います。
親として、子ども同士のトラブルについてどのように対応していけばいいか参考になる本作だが、巻末には、小児科医・今西洋介(ふらいと)先生による放置子についてのコラムもあり、こちらも大変参考になる内容なので、ぜひ読んでみてほしい。
取材協力:白目みさえ(@misae_yjm)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。