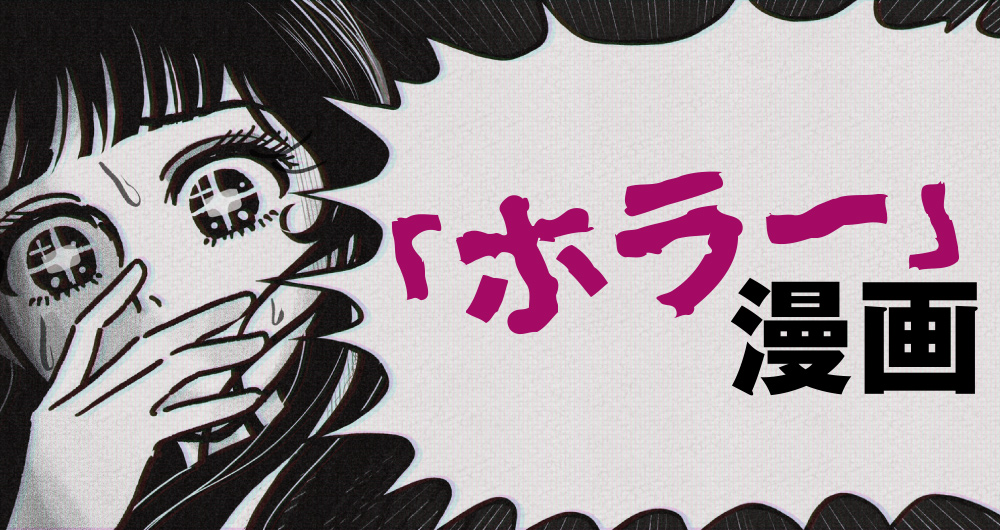制作者はたった2人!ホラーゲーム「ウツロマユ-Hollow Cocoon-」の人気の秘密は“細かすぎるこだわり”にあった

2023年12月7日にValve社の「Steam」にてリリースされた「ウツロマユ‐Hollow Cocoon-」(以下、「ウツロマユ」)をご存知だろうか。
「ウツロマユ」は、ゲーム制作サークル「NAYUTA STUDIO」に所属する、UTUTUYAさんとKOZUEさんのたった2人だけで制作した、いわゆるインディーゲームだ。
1980年代の日本の田舎を舞台にしたこの一人称ホラーゲームは、リリース前からその精細なグラフィックと恐怖の演出で期待を集め、リリース後にはSteamで「非常に好評」と評され、500件に迫るレビューが寄せられた。
また、YouTubeでの実況・考察動画が数多くアップロードされるなど、人気を博しているわけだが、ここまで話題になった理由とは一体?
今回は、そんな「ウツロマユ」の人気の秘密に迫るべく、開発の経緯などの制作の裏側について、NAYUTA STUDIOのUTUTUYAさんに取材を敢行した。

わずか0.5秒のシーンでも作り込む妥協しないゲーム作り
幼い頃からゲーム作りが好きで、自分のゲームをリリースするのが夢だったというUTUTUYAさん。大学生になった頃に無料のゲームエンジンが登場したことで、これまで技術的に難しかったことが可能になり、本格的にゲームを作るようになったという。
UTUTUYAさんが開発したいゲームのジャンルはSFや牧場経営など多岐に渡るが、その中の一つに一人称視点のリアルな和風ホラーゲームの案があり、それが『ウツロマユ』の原点となったようだ。
「僕自身、ホラーゲームは好きでプレイもよくしますしホラーゲームって、実はほかのジャンルに比べるとまだ作りやすいんですよ。場がクローズドの限られた中で話が成り立つので構築しやすいんです。脱出することが目的になってくるので、ロケーションもそこまで必要ないですし、謎解きやストーリーメインのものであればシステムはシンプルにできる。当時は本業もあったので作りやすいというところも重視していたんです」
本作はおおよそ3時間程度のプレイ時間が想定されているので、プレイ側も遊びやすい設定となっている。とはいえ、ゲーム内のマップは想像以上に広く、作り込みもかなり凝っている。UTUTUYAさんは「当初はお屋敷一戸のマップにしようと思っていたんですが、表現したいと思ったものがどんどん増えてしまって、一戸では足りなくなってしまったんです」と開発中を振り返った。

NAYUTA STUDIOはゲームを動かすためのプログラムの構築をUTUTUYAさんが、3Dモデルやマップの制作をKOZUEさんが担当しており、お互いに意見を出し合いコミュニケーションを密にとりながらゲーム制作を行っているという。
「同じ方向を向いている2人だからこそできているというところもあります。外注すると納期に対して思っていたクオリティに達していなかったときに、作りたいものが作れなくなってしまうこともあるので。クオリティを妥協しない人と一緒なので、自分が表現したいゲームが作れていると思っています」
そんな妥協しない2人だからこそ、体験版と製品版リリースの間のたった2カ月の期間でも細かなところを改善し、発売に至ったのだという。そのひとつが作中にミニゲームとして登場する10円ゲームだ。開発当初は1種類の10円ゲームを設置する予定だったが、体験版をプレイしたユーザーの反響が非常に大きく、製品版では種類を増やしたのだそう。なかには10円ゲームだけをプレイする様子を配信するユーザーもいたそうで、UTUTUYAさんも非常に驚いたようだ。
「オープニングで主人公の湊がバスから降りる映像も元々は体験版にはなくて、バスから降りる効果音のみで表現していたんです。しかし、体験版配信の直前にテストプレイをしてみたところ、音だけだとプレイヤーをゲームの世界に引き込む力が弱いと感じたので急遽オープニング映像を作ることにしました。 このバスのシーンのためだけに、デザイナーにはバスの3Dモデル丸々1台作ってもらいました。 ほかにも、たった0.5秒くらいしか画面に映らない電車の3Dモデルをしっかりと作り込んでくれたりと…。 僕はゲームが動くようにプログラムすることしかできないので、いつもクオリティを妥協せずに3Dモデルを作り込んでくれるデザイナーには頭が上がらないです」


たった数秒であってもそのシーンのためだけに妥協せずに作り込んだところが既視感に繋がっているのかもしれない。そうした既視感はプレイヤーの没入感をさらに高め、よりゲームに入り込めるようになるのではないだろうか。「必要最低限のものを作るのではなく、景色の一部にしかならないかもしれないものでも作り込むということも、2人で作っているからこそできること」とUTUTUYAさんは語った。
「ウツロマユ」はUnityというゲームエンジンで制作されているが、新機能や複雑な光の設定など技術的な点には苦労したという。

「制作機会の少ないものはどうしても苦労します。例えば今作でいうと人物や追跡者を作るのには苦労しました。マップや3Dモデルは作るものが多く日常的に作業が必要になる反面、人物は前作以来の5年ぶりの制作とかになってしまうので、モノと比べてスキルが上がりづらくて毎回苦労します。プロモーション映像も同じような理由で、1作品につき基本1つしか制作しないので、毎回動画編集の勉強をしながら作成しています」
プログラムやモデリングに比べて人物モデルや動画編集などは数年ごとになってしまうため、スキルがなかなか培えず毎回苦労することも多いようだ。その一方でゲーム作りが苦しくなることはほとんどなく、一日中ゲームを作っていてもゲーム制作自体が楽しいのだそう。
リリース前から配信されたスクリーンショットやトレーラーを見た人からグラフィックの美麗さ、一人称視点の和ホラーというジャンルから大きな期待が寄せられていた。リリース後はグラフィック以上に物語への反響が大きかったそう。物語重視で制作していたため、こうした声はとてもうれしかったという。
「開発中、自分ではこのゲームがおもしろいのかわからないんです。おもしろくないので はないか、物語がプレイヤーにちゃんと伝わるのかといった不安に何度も襲われました。でも実際にゲームをプレイした人の配信を見ていたとき、物語に感動して泣いてしまう人もいて、自分たちが作った物語が絶対値の大きい感情を生み出すことができたと感じて本当にうれしかったです」

不安に駆られながら「本当におもしろいのか」がわからないまま開発し、トレーラーや体験版で期待感が上がっていたのもうれしい反面ちょっぴりプレッシャーにもなっていたそう。しかし、ウツロマユをプレイした多くの人が物語に感動し、小ネタや別エンディングを見るために何度も周回プレイするようになり、SNSやYouTubeでは配信動画や解説・考察動画などが多くアップされ、話題を呼ぶこととなった。
プレイヤーを置き去りにしない「没入感」を大切に
「ウツロマユ」の時代背景は現代ではなく、1980年代が設定されている。その理由のひとつに怪物や異形の存在がSNSの発達した現代に登場すると違和感が出てしまうように感じたからだとUTUTUYAさんは話した。
「1980年代は僕自身も生まれていない時代ではあるのですが、オカルト番組がたくさん放送され、オカルトブームであったということは知っていました。妖怪や異形の存在が“いるかもしれない”と思われていた時代設定にすることで、リアルな日本というコンセプトに沿うことができると考えました」


自分が生まれる前の時代というだけでも時代考証には苦労したそう。なかには鍵の開け方が当時と異なるという指摘もあったそうだ。物語の舞台としての違和感のなさ、現代人でも入り込める没入感、1980年代のリアリティを、できる限り考証し表現に努めたという。
リアルなグラフィックや細かなオブジェクトによる作り込みはほかのゲームではそうそう味わえない臨場感と没入感のある「ウツロマユ」。加えてサウンドエフェクトについてもかなりこだわったそう。
「実は、主人公の息遣いが朝と夜で違うんですよ。さらに、敵が視界に入った時や、隠れている時でも敵が近くにいるかいないかでも息遣いにバリエーションを持たせています。一人称視点のゲームのメリットはよりゲームに入り込むことができるという点です。そのメリットを活かすために、音にもかなりこだわりました」

ホラーゲームはプレイヤーに恐怖を与えるゲームであり、その特性上、場を構成する情報が少ない傾向がある。音の種類や大きさもあまりなく、敵が出現しないときは操作キャラクターが発する音のみとなる。そのため、より臨場感や緊張感が増すように規則性がある音ではなく、ランダム性が出るように作ったのだそう。
「息遣いのほかに、かなりの種類の足音がランダムに出るようにもしています。人間って常に同じ音を出して動くわけじゃないと思うので、音の出方、高低も違うようにしています。あとは、風などの環境音や家鳴りもランダムで発生するようにしているんです」
さらに、ファイル・資料を読んで物語を進めるゲームであるゆえに、テキスト作成にもかな り気を配ったという。2人で開発していることもあり、登場人物を少なくして“テキストを読むことでストーリーが明らかになっていく”という手法をとったため、テキストが物語のすべてとなっている。そのためキャラクターが画面に映っていなくても人物像を想像できるような、人間性が伝わるような文章になるように努めたという。 また、プレイヤーが物語から置いてきぼりにならないよう、序盤のテキストには違和感が生まれない程度に、「妻」や「おじいちゃん」など、登場人物の立場を明確にする言葉を多く入れる工夫もしているとのことだった。

困ったときは「バイオハザード」を参考に…お手本であり目標の作品
ウツロマユをプレイした多くの人が往年の人気ゲームタイトルを彷彿とするという感想を述べており、「バイオハザード」や「サイレントヒル」「SIREN」などから影響を受けているのではないかなどの声も多く見られていた。しかし、UTUTUYAさんに影響を受けた作品について伺ってみたところ、意外にも映画作品が多く挙げられた。
「学生の時に見た『REC』(2008年)というスペイン映画がありまして、主人公のカメラマンが撮影した映像で展開されるいわゆるPOVホラー映画なんですけど、臨場感と一人称視点の怖さがすごく伝わってくる映画だったんです。特に、ラストシーンがかなり怖くて。ウツロマユではこの作品を怖さの目標にしていて、この映画で感じた恐怖を表現できたらという思いがありました」
加えて、「サイン」(2002年)から宇宙的存在の怖さや演出なども参考にしているのだとか。ゲーム序盤、主人公の湊が祖母・絹の家に到着した後、玄関から音がして出てみるとそこには鶏の死骸があり、直後に黒電話の音がするというびっくりシーン。この電話の音はまるで耳元で鳴っているかのように大きいのだ。

現実であれば遠くで鳴っている電話がここまで大きな音では聞こえないが、「サイン」ではこうした演出的な手法を使っていたので参考にしたという。「カットシーンではプレイヤーは自分で操作するのではなく、受身の状態になるので、映画の表現はかなり参考にしました」とUTUTUYAさんは当時を振り返った。
「ゲーム性の面では『バイオハザード』を参考にしました。困ったら『バイオハザード7』や『バイオハザードRE2』を見るようにしていて、特にUI※を参考にしていました。なので、バイオファンの方には既視感を覚えた人も多いのではないかと思います。現実にはないけど、ゲームとして誇張した表現をしたい時は『バイオハザード』でもやっているか な?と確認してから実装することもありました。決して追いつけるとは思っていないんですが、ゲームとしての目標は『バイオハザード』でした」
※UIとはユーザーインターフェイス(User Interface)の略称で、ボタンやメニュー項目など、ユーザーが見たり操作したりするゲーム画面上の表示及び動きを指す。

「ウツロマユ」にはメインストーリーのほかにもプレイヤーを魅了する小ネタが多く散りばめられている。その中でも特に序盤の商店の軒先やセーブポイントなどに置かれている10円ゲームは、10円ゲームを延々とやるだけの配信がされるほどの人気が出たミニゲームだ。現代ではめっきり見なくなった懐かしいゲームで逆に目新しく、単純な操作で結果がすぐに出る点が人気なったのではとUTUTUYAさんは推測する。

「せっかく遊んでもらうなら、何かもらってうれしいものが景品になった方がいいと思いまして、あたり券の利用方法を本編2周目以降で使える解放アイテムにしました。10円ゲームを活用するためにこのような仕様にしたのですが、これは開発者のエゴでもあるなと思っています。追加エンディングが10円ゲームをクリアしないと見られないようになっているわけですから。でもある程度調整はしているので、一度でもクリアすればエンディング分は回収できるようにしているので。それでも難しければ台を叩いてもらって…(笑)」

気になる次回作は協力型!全く違ったコンセプトに!
UTUTUYAさんとKOZUEさんの開発名義であるNAYUTA STUDIOの由来は多くの数量を表す那由多(ナユタ)からつけられており、その名前には「たくさんの人に作品を遊んでもらいたい」、そして「プレイヤーに遊んでもらった分だけそのゲームの世界がある」という思いがこめられているのだという。そうした思いから、開発側としてストーリーの答えは用意されているが、プレイヤーが考えてくれた世界や考察もまた正しく、否定することはしたくないので、明確なアンサーをゲーム内で明かさないそうだ。
「ゲームを作った時点での完成度を100とすると、ゲームをプレイした人の想像や考察で120になってくれたらいいなと思っています。映画を見た後に『あれってこういうことだよね』とおしゃべりする時間が僕は大好きで、そういった時間を生み出す作品を作りたいと思っています。僕とKOZUEの2人で描ける世界は限定的なのですが、考察をしてもらえることで僕らが描ききれないところにまで思いを馳せてもらえたら嬉しいです」

気になるのは今後、ウツロマユの続編は出るのかどうか。ファンの中には続編を希望する声も多く寄せられている。それに対して、UTUTUYAさんはきっぱりと「ウツロマユはこれで完結です」と言い切った。
「僕たちは常にゲームを100の完成度で発売することを目指しており、ウツロマユでやりたいことはすべて出し切りました。 なので、ウツロマユという作品はこれでおしまいです。でも、今後別のゲームで世界観の繋がりや、オマケ程度にちょっとウツロマユの要素にふれるというような小ネタを仕込んだりすることはあるかもしれません。次回作については以前から興味があったゲームエンジン『Unreal Engine』を勉強しつつ、現在開発中です。ウツロマユとは世界観やコンセプトは全く異なり、自分の身を蝕む恐怖をテーマにシングルでもマルチプレイでも遊べるゲームを予定しています」

独自の世界観と細部までこだわったゲーム性や3Dモデルの作り込みが、次回作にもいまから期待が高まる。たった2人のスタッフが手掛けるNAYUTA STUDIOの今後の展開が楽しみでならない。
文・取材=織田繭(にげば企画)