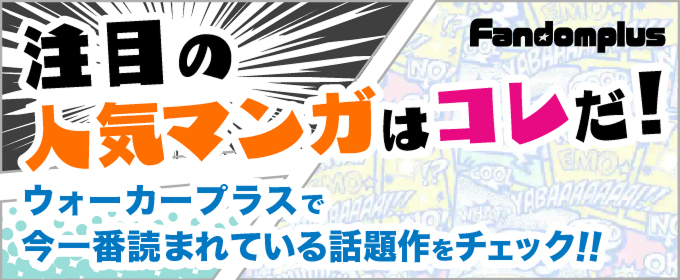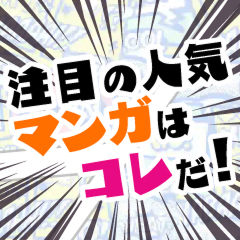【小鳥を飼う難しさとは?】繁殖は命がけ!鳥さんの体に大きな負担がかかる発情について、知っておきたいポイント【獣医師に聞いた】

コロナ禍以降、ペットの需要が高まっている昨今。特に小鳥は見た目のかわいさと、「散歩をしなくていい」「犬や猫と違ってしつけがいらない」など手軽に飼えそうなイメージもあって、人気を博している。しかし、「鳴き声が大きい」「問題行動を起こすためトレーニングが必要」といったケースもあり、「思っていたのとは違う」との理由から、手放してしまう人もいるのだとか。
ウォーカープラスでは、小鳥を飼いたい人や飼い始めたばかりの人に知ってほしい知識や注意点を伝える連載「トリ扱い説明書」をスタート。3羽の小鳥と暮らす鳥野ニーナさん(
@sinamomomomo
)の漫画と、「森下小鳥病院」の院長・寄崎まりを先生の監修&エッセイで、わかりやすくお届けする。
今回は、メスの鳥さんの発情について。快適な環境の飼育下では一年中発情しやすいと言われているが、過剰な発情は体に大きな負担がかかるそう。鳥さんの健康を管理するうえで重要な発情の管理について、紹介する。
「1羽で飼育しているメスが卵を産んだ」と驚く人も。



「繁殖季節」は鳥種によって異なり、時期が決まっていることが多いが、家で飼育されているペットバードは、エサが豊富&適温でさらに夜遅くまで明るい環境で暮らしているため、繁殖季節に関わらず一年中発情をしてしまう傾向にあるという。
なぜ鳥さんの発情にはリスクが伴うのか寄崎先生に尋ねてみると「卵を作る際、体には大きな負担がかかります。発情すると肝臓で、卵の黄身の成分であるタンパク質や脂質がせっせと作られ、血液を介して卵巣へ。そのため、発情が長く続くと肝臓が疲れて悪くなったり、血中の脂質が血管にくっついて動脈硬化が起こりやすくなります」と答えてくれた。
また、1羽で飼育している場合でも、栄養状態が十分なメスは無精卵を産んでしまうため、発情対策が必要とのこと。「メスの発情抑制で一番大切なのは、『体重の管理』です。鳥さんは発情すると卵を作る準備で卵管や卵巣が発達したり、骨にカルシウムを貯めたりするため、普段より体重が重くなります。適正体重を知り、それを維持するよう体重を管理することで産卵を防ぐことができます」と鳥さんの発情抑制のポイントを教えてくれた。
作者の鳥野ニーナさんは、産卵が原因でメスのブンチョウを亡くした経験があるのだそう。「悲しい出来事を防ぐためにも発情のサインを見逃さず、きちんと抑制することが大切です」と注意を促した。
自然とは違う環境下で暮らす鳥さんだからこそ、気をつけてあげたい発情や産卵のこと。日頃からの健康管理が肝心なようだ。
取材協力:「森下小鳥病院」院長・寄崎まりを先生、鳥野ニーナ(@sinamomomomo)