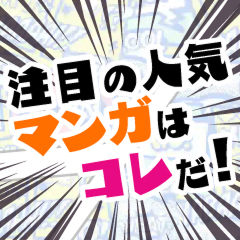「これプラモ…?」貴重写真を参考に“艤装中の戦艦大和”を立体化「船体の各部位はほぼ手作業で製作しました」

対象となるモノの形状を、スケールに基づいて忠実に再現した模型のことを指す「スケールモデル」。船や航空機、戦車、鉄道車両などに加え、アニメや映画といったフィクションに登場する架空のメカなどを製作するモデラーもいて、それらの展示イベントは毎回大盛況となっている。
本稿では、200分の1スケールで戦艦大和を製作し、SNSに投稿しているモデラー・あに(@aniu2)さんにインタビューを実施。製作にいたる経緯や、製作過程で苦労したポイント、この作品を通じて学んだことなどを振り返ってもらった。
共同作業だからこそ、イメージの共有は大切
――本作品を製作するにあたり、どのようなアイデアやインスピレーションがありましたか?
【あにさん】大和が呉の海軍工廠で艤装(船体ができたあと、航海・戦闘に必要な各種の装備を整えること)しているところを撮影した有名な写真があるんですけど、こちらはその場面を再現したものです。実在のシーンをそのまま再現するスケールモデルづくりはあまり経験がないのですが、「この場面をジオラマにできたら間違いなく素晴らしい作品になる」と確信し、製作を決意しました。
それと、せっかく作るのであれば大きいほうがいいと思い、200分の1スケールに挑戦したのですが、ひとりでは手に負えそうになくて……。よく一緒にジオラマを作っている友人のtakaさんに相談して、共同で製作することになりました。

――製作過程で特に難しかった部分は何でしたか?
【あにさん】資料集めに苦労しました。大和は徹底した機密保持ゆえに、艤装(ぎそう)中の姿がわかる正式な写真は1枚しか残っていなくて。写真に写っていない部分や鮮明ではない箇所については、さまざまな書籍を読み漁り、想像で補うしかありませんでした。
その次に大変だったのは船体の製作です。艦橋や主砲はキットを改造する形で対応しましたが、200分の1の船体となると、手に入るキットは皆無で……(※)。そこで代案として、350分の1スケールのタミヤ製キットを購入して。そちらを手に取って形状を確認しつつ、新たに図面を作成し、プラ板からフルスクラッチで作り上げました。
(※かつてニチモから発売されていた200分の1スケールの大和は絶版となり、中古市場では驚くほどの高額がつくプレミアムモデルになっています。ちなみに、このジオラマを作り終えたすぐあとに、モノクロームより待望の新作大和が発売されました)

――今回の製作において、もっとも楽しかった部分は何でしたか?
【あにさん】戦艦大和について詳しく知れたことです。製作するに当たりたくさんの資料を読み、調べることで、大和という巨大建造物の魅力を細かく把握することができました。大和が生まれた理由・目的であったり、一つひとつの部品にどのような意味があったのかなど、いろいろ知ることができたのは楽しい作業でした。

――この作品のなかで特に気に入っているポイントはどこですか?
【あにさん】特定の部位ではなく“作品全体に対する捉え方”になるのですが、大型のスケールモデルを製作する際、細かなパーツ一つひとつに注力しすぎると、それらを組み合わせたときに全体のバランスがおかしくなってしまうことがよくあるんです。今回は最初から、takaさんと入念にイメージの共有・すり合わせをしたうえで製作に当たったので、作品全体のバランスが崩れることなく、当初のイメージ通りに仕上げることができました。その甲斐あって力強い作品を作り出すことができたので、気に入っているポイントを挙げるとしたら、“今回の製作のスタイル”ということになります。

――この作品を通じて、スケールモデル製作における新しい発見や学びはありましたか?
【あにさん】200分の1というスケールでのフィギュアや小物、さまざまな部品の製作は、手作業ではほぼ不可能に近くて。3Dプリンターの恩恵がなければ、この壮大なジオラマの実現はあり得なかったと思います。しかし、それと同時に3Dプリンターの限界も感じました。
確かに、すべてのパーツをデジタルモデリングで製作可能な時代は、すぐそこまで来ているように思います。ですが、今回の作業を通して改めて実感したのは「デジタルモデリングには手作業のような触感や偶然の要素がない」ということです。実際に手を動かし、素材に触れることで生まれる意外性や創造の醍醐味。それこそが“ものづくり”の魅力だと感じました。これからの時代は、スケールモデルやジオラマの製作においても、デジタルとアナログをバランスよく融合させたアプローチが必要だと思います。
取材・文=ソムタム田井