スタバ地元密着プロジェクト、第3弾は“木が息づく”飛騨高山を舞台に
東京ウォーカー(全国版)
スターバックスが2015年より始めた「JIMOTO made」シリーズは、日本各地で受け継がれる伝統技術を取り入れた商品開発を行い、地元の店舗だけで販売し、そのプロダクトを通じて地元の産業や人々のことを知ってもらう機会を生み出すプロジェクトである。

第3弾は飛騨高山。これまではガラス工芸や陶芸が中心だったが、今回は初となる木製のマグカップ。2月10日(金)から、高山市内にあるスターバックス コーヒー 高山岡本店で限定販売される。(※第3弾として「コーヒアロママグTobikanna」も同日発売)


同店は観光地として知られる高山市内にあるものの、来店者の多くが地域の人々という地元に根付いた店。地産地消を取り入れてデザインされた店内は、温もりを感じさせる落ち着いた雰囲気。


目を引く店内中央のアートワークは、木材で世界のコーヒーの生産地が描かれたもの。木材は地元の家具メーカーから譲り受けた端材が再利用されている。

さらにコミュニティテーブルの天板や壁・天井にも岐阜県産の杉材を使用。店舗の内装からも地元との深いつながりを感じる。

コーヒーを堪能したあと、店のスタッフたちとともに、マグカップを製作する高山市内の山間にあるオークヴィレッジへ向かった。
林業の再興を願って、国産の広葉樹を有効活用

オークヴィレッジは1976年に高山市で創業。「循環型社会を目指したモノ造り」を掲げ、家造りや木製品の製造販売を行っているメーカーである。同社を語るうえで、特筆すべきポイントは、創業以来、国産の広葉樹材林を使い続けていること。理由はひとつ、日本の林業の未来を切り開くためだ。


現在、日本の林業は衰退の一途を辿っている。1940~50年代にかけて、戦後復興によって急増する木材の需要に応えるべく、政府は拡大造林政策を行った。これは広葉樹からなる天然林を伐採し、そのかわりにスギやヒノキといった成長が早く、経済的な価値の高い針葉樹の人工林を増やす政策だ。1960年代に主要な燃料が電気やガスに切り替わると、天然林の価値はさらに薄れたが、建築材として価値のある針葉樹を増やすために、拡大造林はさらに加速した。
そんななか、1960年代に海外からの木材輸入が自由化。この出来事が日本の林業に大きな打撃を与えた。円高を追い風に、安価で安定供給ができる外国産の木材の需要は高まっていった。そんなあおりをまともに受け、国産の木材の利用は落ちていったのだ。

オークヴィレッジの取締役、佐々木一弘さんは語る。「輸入された木材の需要が高まるにつれ、国産の木材の価値は下がり続け、日本での林業は衰退してしまいました。山を見れば、拡大造林によって植えられたスギがたくさん生えているようにも見えますが、需要バランスが悪いため、伐採されず長年放置されているものも多いです。日本中に木材は余っているのに、国内での木材の自給率はわずか3割。この現状をなんとかするには、国産の木材を積極的に使って日本の林業を活性化させるしかありません」。

そこでオークヴィレッジが注目したのが、ケヤキやカエデ、ブナ、ナラといった広葉樹だった。その名の通り平べったく幅の広い葉を持ち、枝を横に伸ばして成長する広葉樹は、雨の多い温暖な気候を好み、太い幹を持っているのが特徴だ。

「日本の森には、良質でありながら、流通規格外ということで、活用できていない木々がたくさん存在しています。それに広葉樹は木材として、比較的重くて硬く、生活の道具の素材として使うにも、針葉樹にはない美点や特性があります。日本人は広葉樹を木材として暮らしの中で適材適所に使ってきました。我々は種類の豊富な国内の広葉樹の魅力を発信することで、忘れ去られつつある日本の木材の価値を広く知ってもらいたいと考えています」。
地元の産業や文化に根付いた温故知新のモノ造り

「JIMOTO made」シリーズのために製作されたマグカップにも、国産のトチとホオが使用されている。「いずれも日本の広葉樹の代表的な品種です。伐採による自然への影響が少なく、硬いのに刃物の当たりがよくて加工しやすい。それに漆ののりもいい。迷わずこの木材を選びました」。


まずはオークヴィレッジ周辺を散策して広葉樹林を観察することに。周辺の山々には、自然の広葉樹林が残り、愛情を込めて管理されている。広葉樹の枝にたくさんの雪が降り積もった木々が、幻想的なムードを醸し出していた。


次は高山市のカネモクへ。同社は原木の仕入れから製材、乾燥、木取り(カット)までを一貫して行う製材所。飛騨地方でも広葉樹だけを専門に扱う製材所は希少である。

「広葉樹の扱いには、針葉樹とは異なる専門的なノウハウや技術が必要とされます。カネモクさんは伝統的な技術を受け継いでいるだけでなく、今も熱心に研究を続け、日々技術を向上させています」と佐々木さんからの信頼も厚い。

まさに伝統芸。製作するものや樹種によってカットの仕方は異なるし、乾燥させる時間も樹種や状態、気温や湿度に応じて見極めなければならない。


次に向かったのはオークヴィレッジグループの森林たくみ塾。1991年、飛騨高山に設立された日本初の木の総合教育機関では、次世代を担う職人の育成をしている。
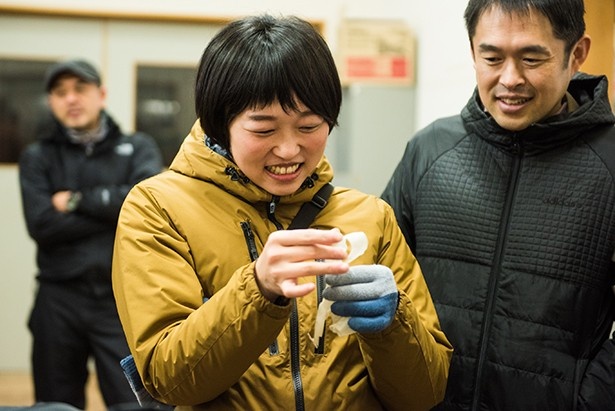
この塾の学費は無料。学生たちは技術を学びながら、モノ造りをサポートしていくのだという。佐々木さんもここで木工を学んだOBのひとりだ。「木の文化を後世へ受け継いでいくためには、技術を持つ人材の育成が不可欠です。木工のほか、広葉樹の森林づくりなど幅広い活動をしています」。

オークヴィレッジへ戻り、いよいよこのマグカップのハイライトである「漆塗り」の工程を見学。「漆を使った商品を作り続けています」と佐々木さんは「漆塗り」の素晴らしさを説明してくれた。
絶妙な風合いを生み出す「漆塗り」職人の技術

京都で漆塗りを学んだ女性職人の荒川さんが「拭き漆」という工程を披露。コシのある刷毛筆を前後に動かして、木目に生漆を何度も塗り込んでいく。


木目によって漆の入り方が微妙に異なるため、全体の色みを均一にするためには、木目を読む長年の経験が必要とされる。2、3度塗るごとに手で磨く。この作業を繰り返すにつれて、色の深みと表面の輝きが増していく。

「拭き漆は透き通ってカップの木目がくっきりと浮かびあがり美しい。使うほどに赤みが和らいで、色が落ち着き、優しい雰囲気になっていきます。漆塗りには器を丈夫にして水漏れを防ぐ役割もあります」と語ってくれた荒川さんの笑顔が印象的だった。

漆を塗って、乾燥させたら、装飾を施す「加飾」と呼ばれる工程へ。使うのは白と黒の特殊な色塗塗料。漆の器への細かな紋様の絵付けは難度が高く、ひとつひとつ木目の違う器に高い精度で加飾することに苦労したという。

ホワイトの幾何学模様は民芸品の刺し子がモチーフ。刺し子は布地に糸で図柄を刺繍する手芸の一種。雪深い飛騨地方では、冬の間、家の中で主婦たちがこの民芸品を作り続けてきた。

ブラックの模様は国史跡の高山陣屋から着想を得たもの。高山陣屋は江戸時代における幕府支配の拠点となった役所で、郡代役所の主要な建物が残っているのは全国でもここだけ。幾何学模様をよく見るとうさぎの姿が。これは陣屋の欄間などに見られる有名な図柄である。


最終工程は取っ手の接着。ボディは曲面で、そのうえ表面には漆が塗られている。このボディに一点一点取っ手を接着するためには、繊細な手仕事が要求される。


こうして「ウッドマグ漆ホワイト/漆ブラック」が完成した。モダンなフォルムと和の素材、匠の技が渾然一体となった唯一無二のデザインだ。


取材後は恒例のレクリエーションタイムへ。スターバックスのスタッフたちからのさまざまな質問に、オークヴィレッジの担当者が丁寧に答える。
このプロジェクトの目的は、地域とゆかりの深いプロダクトを通じて地元コミュニティとのつながりを深めることにある。そのためには、店頭で商品を販売するスタッフと作り手とのコミュニケーションが必須だ。作り手がプロダクトに込めた思いは、スタッフを通じて店の客へと伝達されていく。

「このマグカップを通じてお客様に伝えたいことはなんでしょう?」というスターバックスのスタッフからの質問に佐々木さんが答える。「マグカップに込めた思いは2つあります。まずは飛騨高山という土地の魅力をもっと知ってほしい。そしてもうひとつは、日本の林業の希望になってほしいということ。日本は、国土の約7割が森林という世界第3位の森林大国です。さらには日本では歴史的に広葉樹は暮らしに活用され、世界に誇る木の文化が育まれました。にもかかわらず、現代の日本では国産の木の魅力が忘れ去られつつあります。このマグカップが、日本の木と文化を今一度考えるきっかけになることを願っています」。


木材から製法、漆、紋様にいたるまで、地元の叡智が結晶されたマグカップは、飛騨高山という土地の魅力だけでなく、日本のモノ造りそのものの力を証明するマスターピースだ。【ウォーカープラス編集部/取材・文=押条良太、写真=夏目圭一郎】
※一部欠品の可能性があります
押条良太
この記事の画像一覧(全40枚)
いまAmazonで注目されているスターバックスの商品
※2025年12月18日12時 時点の情報です
-

スターバックス カフェ モーメント スムース 65g,レギュラー ソリュブル コーヒー,約32杯分,ミディアムロースト
新品最安値:1,070円
-

スターバックス オリガミwithマグカップ ギフト SBC-30B,レギュラー コーヒー,ドリップ
新品最安値:2,889円
-

【ドルチェ グスト オリジナル専用(ネオ互換性なし)】スターバックス ハウス ブレンド ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 60P,箱,レギュラーコーヒー,ブラックコーヒー,ポッド
新品最安値:5,250円
-

スターバックスプレミアム ミックス ギフト SBP-20B,スティック コーヒー
新品最安値:1,780円
-

サントリー スターバックス MY COFFEE TIME カフェラテ 缶コーヒー 185g×30本
新品最安値:3,548円
キーワード
テーマWalker
テーマ別特集をチェック
季節特集
季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介
全国約1100カ所の紅葉スポットを見頃情報つきでご紹介!9月下旬からは紅葉名所の色付き情報を毎日更新でお届け。人気ランキングも要チェック!
全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!
おでかけ特集
今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け
キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介






