タザキの投資本案内「マネーの公理 スイスの銀行家に学ぶ儲けのルール」/正しく「賭けて勝つ」ためのルールとは
東京ウォーカー(全国版)
こんにちは。YouTubeチャンネル「聞いてわかる投資本要約チャンネル」を運営している、二児の父でサラリーマン投資家のタザキ(
@tazaki_youtube
)と申します。
学生時代に株の魅力を知って以来、投資本好きが高じて自分の学びをYouTubeで発信したところ、想像以上の反響を呼び、3年間でチャンネル登録者が10万人を超えました。これまでに読んだ投資・マネー系の本は300冊以上。
その経験から、ここでは特におすすめの書籍や、コスパの高い書籍を、経験値や投資スタイル別で紹介していきます。本日紹介する
「マネーの公理 スイスの銀行家に学ぶ儲けのルール」(著:マックス・ギュンター/日経BP)
は、1976年に英国で出版されたロングセラーです。
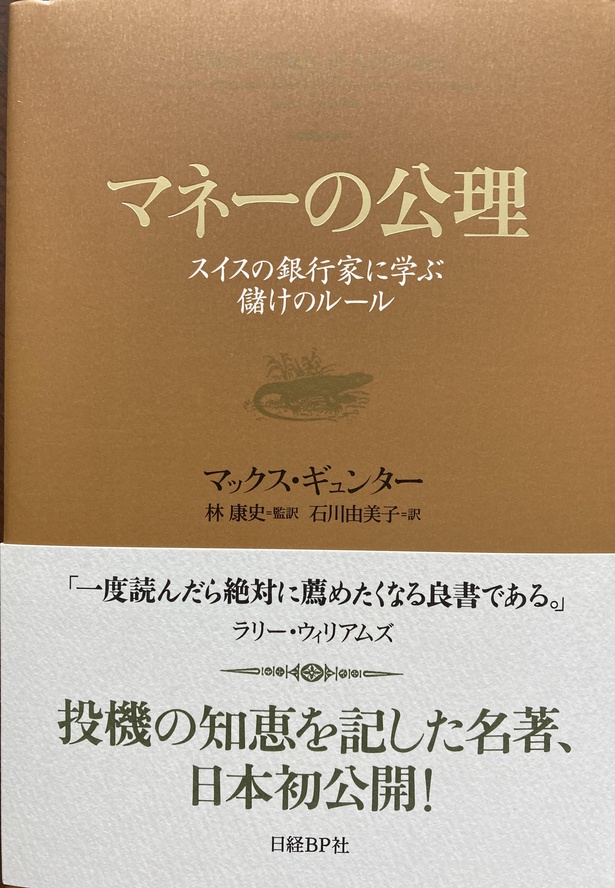
本書は、スイスの銀行家から「投機の神髄」を学べるものになっています。
スイスは一人当たりGDPが世界でも上位で、通貨のスイスフランは世界中の投資家から安全資産とみなされています。
スイスがこれほどまでに豊かな国となったのは、スイス人が世界でも優れた投資家であり投機家であることが一因とされています。本書では彼らの「合理的に賭けて勝つ」哲学と、その具現化である12の公理が解説されています。勝つためにはリスクを避けるのではなく、受け入れるというスタンスですね。
じっくり農耕型で育てる「投資」ではなく、積極的で狩猟的な「投機」を行う場合にこそ、同書のよさが感じられることでしょう。
リスクを取ることは、普通の人が富裕層に昇格するための唯一の方法です。なんて言うと、「そこまでして金持ちになりたくない」「心の平穏の方が大事だ」と感じる方もいるかもしれません。これは価値観も関係するかもしれませんが、同書では、リスクを意図的に取る、冒険的な挑戦をすることが、真の幸せにつながるとされています。個人的には、けっこうチャレンジングな性格なので、共感できます。
もちろん、破産するほどのリスクを取るべきではありませんが、
「一定のリスクを取らなければ何も現状は変えられない」ということを実感できるかと思います。
市場のカオス:「絶対法則」という幻想と独自の投資スタンス
まず、第五の公理「パターンについて」を取り上げたいと思います。そもそも市場というのはカオスであり、絶対的な法則は存在しません。しかしながら、そのカオスの中で法則を見つけ出そうと試みるのは、人間の性ではないでしょうか。しかし同書は、市場には確固たる法則が存在すると信じ込むことは、「チャーティストの幻想」のようなものだと指摘します。
なぜ、こんなにも我々はカオスの中で法則を見つけ出そうとするのでしょうか。それは人間が法則性を発見することに「安心感」を得るからと考えられます。しかし、重要なことを再度強調します
。市場には絶対的な法則は存在しません。「整然とした法則が見え始めた」と感じたら、それは危険なサインです。
当然、「大多数の意見」の中にも正解はありません。ギャンブルで勝つ秘訣は、自分が納得するまで他人の意見を無視することだと言われています。「人の行く裏に道あり花の山」という格言はよく投資においても使われますよね。
投資の世界で利益を得るためには、大衆とは逆の行動を取る―つまり、流行に迎合しないことが重要なのですね。
最良の買い時とは、誰もがその投資を避けているときに購入すること
のようです。
自信たっぷりの銘柄を、軽く持つ
第十一の公理「執着について」は個人的には特に傑作だと感じています。もし、
最初から計画通りにうまくいかない場合は、その銘柄をチェイス(追いかけ)せずに距離をおくこと。
つまり、損切りや利食いですね。
これと反対の行動として、さらに追加投資をする「ナンピン買い」がありますが、それはあまり適切ではないとされています。なぜなら、ナンピン買いは実質的に自分自身を騙す手法だからです。
ナンピン買いしているときの思想は時折、落とし穴にもなります。自信満々の銘柄を見つけたとき、それがどうにも思うように伸びない。市場は間違っていて、自分の判断が正しいと思い込んでしまうことがあります。私もかつて、自分のアイデアに固執していました。しかし、本書を読み、1つの銘柄や1つのアイデアに執着してはならないと学びました(今でも完全に、1つの銘柄への固執を断ち切れているわけではありませんが…笑)。
自分が選んだ銘柄が思うように伸びないときは、執着せず、自分が間違っていると素直に認め、必要なら素早く後退することが大切です。
なぜなら、目的は自分の考えの正しさを立証することではなく、利益を得ることだからです。
当然、毎回勝つことは難しいですが、強力な自信を基に行動を行うことは必要です。
つまり「自信たっぷりの銘柄を軽く持つ」ことを心掛けなければならないと、個人的には痛感しました。「重く」持つべきではありません。なぜなら、そうすると手放せなくなってしまうからです。
その執着を避けるために重要な行動として、「利食い」と「損切り」があります。利食いについては、早期の利益確定を心掛けることが重要です。
「損切りは早く行い、利食いはなるべく伸ばして少しでも大きい利益をとる」という損小利大を目指すスタイルをよく聞きますが、同書では、その利益を少しでも伸ばそうとする心理を「強欲」だとして最終的に損をする可能性が高いと言います。
サッカーでは90分、マラソンなら42.195キロと、ゴール地点が決まっているように、投資や投機でも最初に決めた損切り地点、利食い地点に達したら、そこで投資を止めるべきだとしています。

一方、想定に反して下がって含み益を抱えたときは、「希望を捨て」、早期に損切りをすることが推奨されています。これは納得ですね。小さな損失は、大きな利益を得る過程に必ず何度か発生します。それを受け入れていかなければ、投資や投機を継続することなどできませんね。
直観の種類を見極め、うまく利用する
第七の公理「直観について」もなかなかおもしろいです。直観は人により捉え方が異なります。一部の人々は直観が信頼できないと判断し、常に合理的に行動しようとします。一方で、直観を主に用いて判断する人もいます。
同書では
「直観は説明できるのであれば信頼できる」
と主張しています。直観には種類があり、役立つものもあれば、ただの妄想であって役立たないものも存在します。
シカゴ大学の心理学者ユージン・ジェンドリン博士によれば、「人間が意識できる情報は氷山の一角に過ぎない」。多くの情報が人間の意識の下、無意識の領域に存在します。人間が直観により判断するとき、それは気づいていない無意識の情報が影響しており、その情報に基づいて直観が生まれます。したがって、直観が湧いてくるということは、無意識の中にある何かが働いている可能性があるのです。
それらの直観は単なる妄想ではなく、何らかの理由に基づいていると捉えることができます。ただし、その無意識の情報源は自分でも認識していないことが多いため、それを適切に識別する必要があります。
希望は直観と混同されがちです。「希望的観測」にすがるのではなく、自分の望む結果と直観が混同されていないかをしっかりと識別することが必要です。逆に言えば、悪い直観ほど、自分が望んでいるわけでもないにもかかわらず、それが生じるということは無意識下の何か、特に自分の記憶がそれを引き起こしている可能性があります。事実、悪い直観ほど当たる確率が高いとされていますからね。
日常生活でもよくあるように、投資や投機においても、理由はわからないが何かが不審だと感じるとき、その直観は意外と当たってしまうものです。これは、無意識の中で自分でも気づいていない深層の記憶が引き金となってその直観が生じていると考えられます。
しかし、直観は必ずしも100%信頼できるものではありません。それをうまく識別することが必要で、この本がまさにその識別方法について述べたものになっています。
まとめ
この本では、リスクを合理的に取りながら、どうリスクと向き合い、勝負に勝っていくかという内容に焦点を当てています。
一定の実戦経験を積んできた方にとっては、特に響くかもしれません。スイスの銀行家の投資哲学を学んでみたい方は、ぜひこの本をご覧ください。
この記事の画像一覧(全2枚)
キーワード
テーマWalker
テーマ別特集をチェック
季節特集
季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介
おでかけ特集
今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け
キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介







