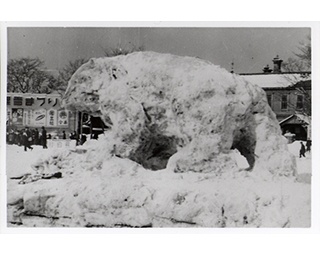さっぽろ雪まつりはここから! ドカンと降ろされた雪が迫力満点!「雪輸送開始式」
北海道ウォーカー
冬の人気イベント「さっぽろ雪まつり」が開催されます。見る人の多くを魅了する大雪像は、会場の大通公園周辺の雪を使っていると思いますよね? 実は遠くからわざわざ運んできているんです! いよいよ始まった雪像づくりを担っているのが陸上自衛隊。今回は雪像制作が始まる「雪輸送開始式」に密着しました!
雪像の雪は札幌市内、市外から輸送される

雪像制作の雪は例年、札幌市内の雪堆積場から大通公園まで運び入れます。いつもは滝野霊園の雪をメインで使用しますが、今年は積雪が少ないため、豊平峡ダムや、真駒内カントリークラブの雪も使用しているそう。大通会場8丁目にできあがる予定の「奈良・薬師寺 大講堂」の雪輸送・制作を担っているが陸上自衛隊。毎日9時から16時まで4トントラック約40台の雪を大通会場へと運びます! 完成までには全体で4トントラック510台分の雪を使用するそう。大通公園から滝野霊園まで約20キロ、豊平峡ダムまでは30キロ以上あり、サラサラな新雪を各所から運んでいます。

いよいよ雪像作りが始まる「さっぽろ雪まつり協力団編成完結式」と「雪輸送開始式」

札幌各所から雪を運び入れ完成する大雪像。そんな大雪像を作り始める日は毎年式典が行われます。今年は1月7日、大通会場8丁目「雪のHTB会場」で「さっぽろ雪まつり協力団編成完結式」が行われました。雪まつりを歓迎するかのように、しんしんと降る雪のなか、敬礼するところから式は始まります。

陸上自衛隊が雪まつりに関わるのは今回で64回目。担任官からの挨拶があり、路面状況の悪いなかでの雪の輸送作業、雪像制作の作業の安全を誓い式典は終了しました。

続いて始まったのは「雪輸送開始式」。第3施設団第303ダンプ車両中隊の山田真矢陸士長と、北部方面輸送隊第313輸送中隊の鹿戸萌実陸士長が、雪まつり協力宣言をしました。そして会場に並んでいたトラックから雪が降ろされ無事に式は終了。

その後、大雪像「奈良・薬師寺 大講堂」制作の安全祈願式。第11旅団18普通科連隊 石川連隊長が「札幌雪まつりは、世界的な大イベントであり、国内だけでなく世界中の人々に夢と感動を与えることが可能な任務。私達は本来の任務である国及び国民の安全を守ることを忘れることなく、立派な雪像を完成させ、自衛隊に興味・関心を持ってくれる方が増えることを期待しています」と挨拶がありました。
そもそも大雪像作りになぜ自衛隊が関わっているのでしょうか?
全国的・世界的にも有名な同イベントで雪輸送、雪像制作をすることで、北海道民に自衛隊への理解・信頼を深めてもらうことが目的なんだそう。雪が降りしきるなか、1か月近く雪像を作る自衛隊の方々には頭が下がる思いです。
最後に安全旗の授与と、安全祈願として雪山にお清めがされました。

こうして無事に式典は終了。トラックから降ろされた高さ3mもの雪山は真っ白でキレイ! ここからどのように雪像が出来ていくのか楽しみですね!
式典が終了すると2月5日から開催されるさっぽろ雪まつり開催に向け、いよいよ雪像づくりがスタートです。
雪像制作は自衛隊ならではの方法も!
今回陸上自衛隊が制作する大雪像は大通会場4丁目「ファイナルファンタジーXIV “白銀の決戦”」と大通会場8丁目「奈良・薬師寺 大講堂」の2基。8丁目会場「奈良・薬師寺 大講堂」はデザインも陸上自衛隊が担当しています。実際に薬師寺に訪問し、細部の把握、そこから模型と設計図の制作。実際の制作では、制作工程を分担して担当します。関係各所との連携や調整を行う「本部班」、制作全般の各種作業を行う「作業隊」、「制作隊」に指示・指導を行う小隊長、班長を中心とした「技術員」がいます。隊員が一致団結し1つの目標を達成する組織力があるからこそ、緻密に再現された大雪像が作れるんですね!

巨大な大雪像は一体どのように作っていくのでしょうか? 話をうかがったところ、実は雪の本体にさまざまなパーツを貼り付けて作っていくのです。そして、最後に真っ白な化粧雪を貼り付け完成! 「アイスブロック工法」と呼ばれる方法だそうです。より細かな部分を表現できる、まさに大雪像を作るための工法。パーツの数は50種類、全4400個! 同じ形のパーツをいくつも作らなければならないため、制作にはセメントで作った型枠を用意。型枠に雪を入れ、固めたものが大雪像を構成するパーツとなります。
パーツの取り付け作業は、気温0度以下又は、夜間に行われます。気温が高いと本体もパーツも溶けてしまい、しっかりと取り付けられないんだそう。

雪像作りにおいて、大切なのは精密に設計した設計図を基に忠実に作成すること、安全に作業することの2つ。また荒削りが主となる前半戦は体力勝負。完成が近づくと細かい彫刻がメインとなる繊細な作業に突入します。雪まつり開催期間中も崩れたら補修しなければならないので、閉会する瞬間まで気を許すことはできない。特に今回の「奈良・薬師寺 大講堂」で難しい部分は「反り屋根」と呼ばれる緩やかな屋根の傾斜。そして屋根の四隅につるされる「風鐸」などのパーツ部分だそう。

本体である雪を荒削りし、寝かせた後パーツの取り付けと仕上げのきれいな雪貼り付けることで、より白く美しい雪像へと早変わりします。これらの作業は雪まつり開催前日まで行われます。
雪像づくりはもちろん無計画に行うわけではありません。日ごとに工程が細かく定められています。今回、8丁目会場「奈良・薬師寺 大講堂」は1月7日~15日で本体となる雪積み作業、17日~21日には大まかな形にする荒削り作業、22日~31日から細かい彫刻部分や屋根のパーツ取り付け、2月1日~3日で仕上げ用の化粧雪をかぶせ、2月4日に完成という流れ。
毎日9時~16時まで制作を行い、22日から状況を見て16時以降も夜を徹して作業を続行し、野外作業は天候に左右されやすく、気温が高かったり、雨が降っていたりすると雪が溶けてしまうので、0度以下の晴天の日が作業しやすいんだとか。

実物を細部まで再現するための現地見学や、札幌市内外からの雪輸送はとても大掛かり。しかし、綿密な事前準備があるからこそ、迫力満点の大雪像が私達の前に登場するのですね。
松山典子
同じまとめの記事をもっと読む
この記事の画像一覧(全11枚)
キーワード
テーマWalker
テーマ別特集をチェック
季節特集
季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介
全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!
おでかけ特集
今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け
キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介