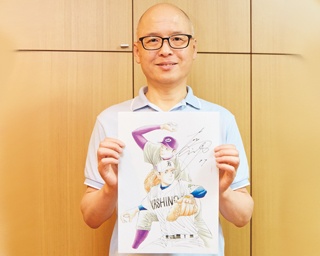高校野球連載 第18回/漫画家・三田紀房が20年通って見た甲子園のドラマと未来
関西ウォーカー
“高校野球大好き”な著名人が甲子園の魅力を語るスペシャル連載「”ワタシ”が語る甲子園~100年の熱狂ストーリー~」。情報誌「関西ウォーカー」と連動してスタートしたWEB版連載では、誌面に掲載しきれなかった未公開トークを含むスペシャル版を前後編で掲載。
連載第18回目は、「甲子園へ行こう!」「砂の栄冠」(共に講談社)など高校野球漫画も手がけ、20年以上も甲子園球場へ通い続ける漫画家・三田紀房先生のインタビュー(前編)をお届け!

漫画のような劇的展開を、甲子園観戦で実感
―高校野球、甲子園に興味をもたれたきっかけを教えて下さい。
三田「従弟が高校球児だったので、試合で応援しているうちに高校野球を身近に感じるようになりました。甲子園へ通い始めたのは『クロカン』という作品を描き始めたころです。取材で訪れ20年以上通い続けてきましたが、特に印象深い試合は、2007年の決勝戦、広陵(広島)対佐賀北(佐賀)戦ですね。バックネット裏で観戦していたのですが、佐賀北が敗戦濃厚なまま試合が進んで『このままいっちゃうのかな…』と思ったんですけども、8回裏に一本ヒットが出てから球場全体の雰囲気が佐賀北応援ムードに急変、一気に満塁ホームランで逆転して、『こんなことがあるのか!?』と驚きました。まさに漫画で描かれそうな展開を現場で実際に体感できて、貴重な体験だったと思います」
―公立校が強豪校を倒す展開も甲子園の醍醐味ですよね。
三田「そうですね。でもチャンピオン同士のガチ勝負も燃えます。大阪桐蔭対横浜とか、意地とプライドを賭けてのスーパーエリートの闘いも僕は好きですね。なかには『野球エリートばかり』的な声もあるんですけども、あそこまで極めるのも突き詰めた努力があるわけで、興味深いです。三役そろい踏みではありませんが、これだけ歴史があると番付上位的な強豪校が定着してきますね。試合でぶつかり合う機会が増えれば大会は盛り上がるし、試合数が増える100回大会は、より期待ができます」
―ほかに面白いと思う展開はありますか?
三田「出場校が会期中に“あれよあれよ″と意外な成長を見せるのも高校野球ならではです。一回戦から二回戦、三回戦、だんだん上手くなっていくし、一回戦ではフォアボールを7、8回出していた投手が準々決勝になると全く出さなくなったり、急にコントロールがよくなっちゃうみたいな。甲子園では意外とあるんですよね。1週間~10日で劇的な成長が見られる場でもあり、高校野球のすごく好きな部分です」
駒苫に応援の重要性を学び、花巻東に東北初の栄冠を期待

―観戦や取材経験、漫画の制作を通して感じた、三田先生ならではの甲子園の魅力・楽しみ方を教えてください。
三田「広陵対佐賀北戦のような試合を観ると、応援も一つのプレーとして楽しめる時代になったなと感じます。甲子園のお客さんの大半は野球を見るだけでなく盛り上がりたいんです。ビールを飲んで、メガホンをたたいたりライブ感を味わいに来ているので、実はどちらが勝ってもいいんです。そういう方々を応援でうまく乗せられると、球場の熱気が上がって相手校にプレッシャーがかかる。雰囲気の変化は見ていてわかるんです。そういう演出の影響力を考えると、応援も勝利のあと押しになると思います」
―応援の重要性を強く意識されたきっかけは、広陵対佐賀北戦のほかにもあるのでしょうか?
三田「2004年、05年の夏の甲子園を連覇した駒大苫小牧(南北海道)の登場が大きかったです。駒苫のブラスバンドはまるでコンサートを聴いているような演奏で、戦況を見ながらの選曲が絶妙なんです。香田誉士史監督(当時)は駒大から楽譜を借りて、ブラスバンドに選曲・演出を細かくリクエストして応援を変革したんです。これは優勝への原動力の一つだったと思いますよ。駒苫以降、応援の傾向も変わってブラスバンドの演奏も向上しましたね。東邦(愛知)も綿密なプランのもと統率のとれた応援をしていて、素晴らしかったです。地方のチームも交通インフラの発達で甲子園に足を運んでアルプスで応援できるようになりました。これからは『応援を活用する』という観点で、もっと進化するのではないでしょうか。『応援で勝つ』ことは、甲子園ならではの重要なポイントです」
―ちなみに三田先生が、特に応援している学校はどこでしょう?
三田「地元・東北勢のなかでも、大谷(翔平)くんや(菊池)雄星くんを輩出した花巻東(岩手)です。雄星くんを擁した2009年の夏は準決勝まで勝ち進んだのですが、そのあとに登場した大谷くんは、甲子園では一勝もできなかったんですよ。まぁ、雄星くんの世代はほかの選手もハイレベルで、20年に一度そろうかというスーパーチームでしたからね。でも、その後はぬきんでた選手がいなくてもピッチャーを左、右、左と3人くらい育てて、試合では辛抱強く粘って最後に1点差で勝つ、そんな立ち回りができるチームになりました。こういう学校が岩手県から誕生する時代になったことが、すごくうれしいですよね。ここまでに100年かかりましたから(笑)。佐々木 洋監督とは個人的にも親しくさせていただいており、『東北で最初に優勝旗を持ち帰ってほしい』と言っていて。監督は『もう出場するので精一杯です』なんておっしゃいますけど、近い将来、実現すると信じています」
球児たちの消耗度が上がった昨今、タイブレークは必然

―夏の甲子園が100回を迎えることについて、何か思うことはありますか?
三田「世界中で100回以上続いている競技大会はいくつあるのかと探してみると、おそらくウィンブルドン選手権(テニス)、全英オープン(ゴルフ)、あとはヘンリー・ロイヤル・レガッタ(ボート)など数えるほどでしょう。つまり、100回という数は世界レベルの権威なんです。甲子園大会は昭和50年代から現在の形式で定着し始めて、回を重ねるなかで新たな価値観をはぐくんできました。大会としては、もはや完成形なんです。なので100回だからとなにかを変えることなく150回、200回と同じように続けてもらいたい。続けることで今後も大会の意義は増していくと思います」
―形式、価値観を育み続ければ、今のままでよいということでしょうか?
三田「もちろん柔軟に考えるべき部分もあります。例えば選手たちの身体・能力的な変化を鑑みての改正は必要で、今回導入されるタイブレーク制が好例です。選手の消耗度は20~30年前と比べて格段に上がっているんです。6割打者の4番5番がたくさん出てくるし9番バッターがホームランを打っちゃうんですから。ピッチャーは1試合で180~200球も投げて、ファールを打たれ続けたらたまったものじゃない。試合内容がハードになった訳ですから導入はやむを得ぬ決断でしょう。先送りして選手が犠牲になる前に歯止めをかけないと。タイブレークは国際試合でも導入されていますし、日本が対応する意味でもいい機会と捉えますね」
―こうした記念大会について、球児たちにどう思うか話を伺われたことがあるとか。
三田「『(出場枠が増えるので)試合が増えるのは…』と、消耗度が増すので大変だと聞いたことがあります。選手は案外そう考えるのでしょうが、学校としては記憶に残る節目でメディアの注目も高まりますし、優勝したい気持ちが強くなるのはわかりますね。特に大阪桐蔭は狙っていますね。西谷浩一監督が2度目の春夏連覇を目指すと公言していますし、それだけのチーム力もあるのでね。その分、智辯和歌山、明徳義塾(高知)など“打倒大阪桐蔭”を掲げる高校も出てくるでしょうし、とても盛り上がるんじゃないかなと思いますね」
◇
〈今回の語り部〉
三田紀房(漫画家)/1958年生まれ。岩手県出身。東大受験漫画「ドラゴン桜」で人気を集める。現在、週刊ヤングマガジンで「アルキメデスの大戦」、週刊モーニングで「ドラゴン桜2」を連載中
【現在連載中の三田先生の作品もチェック】
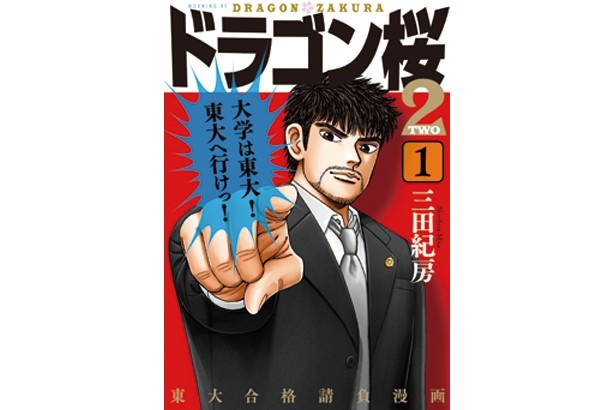
「ドラゴン桜2」…東大合格請負人と呼ばれた伝説の弁護士・桜木健二。2020年の教育改革を前に龍山高校に戻った彼が再び改革を断行する。
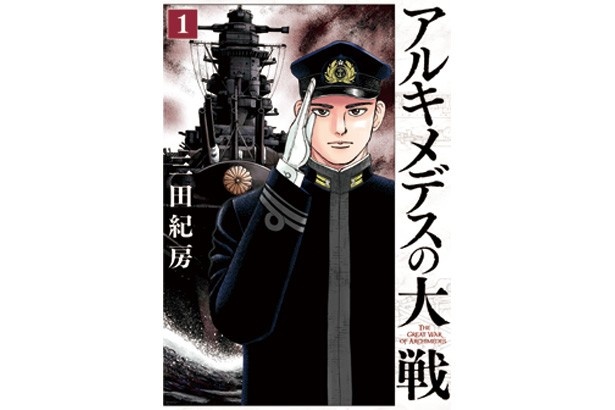
「アルキメデスの大戦」…日本と欧米列強の対立が激化した1933年。大型戦艦を推す海軍で航空機への転換を図る山本五十六は、ある男に使命を託す。
トライワークス
同じまとめの記事をもっと読む
この記事の画像一覧(全5枚)
キーワード
テーマWalker
テーマ別特集をチェック
季節特集
季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介
全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!
全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!
おでかけ特集
今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け
キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介