【最終回】連載第31回 2019年「愛しあってるかい!名セリフ&名場面で振り返る平成ドラマ30年史」
東京ウォーカー(全国版)
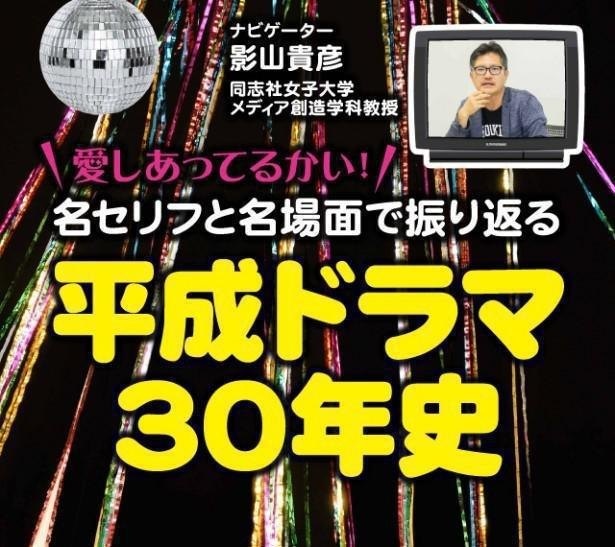
エンタメから目をそむけるな。Let’s think!
ついに2019年。平成が終わりを告げ、令和という名の新しい時代が始まった。「昭和・平成・令和と3つの時代を生きることになりました。様々な事件やエンタメの流れから、ジワジワと世の中が変化しているのを感じます。平成は明治以降、戦争を経験しなかった唯一の時代。その『平和』をしっかりと令和にバトンタッチしなければならないですよね」。そう語る影山貴彦氏と振り返る、平成最後のドラマ。そして令和に向けてのエンタメはどう進むべきか。その課題と期待は…。
―まず、平成と令和をまたいだ4月放送開始(4~6月)も含め、平成31年、印象に残っているドラマを教えてください。
「きのう何食べた?」からいきましょう。2018年の「おっさんずラブ」では、友人や仕事仲間も巻き込んでの純愛が描かれましたが、「きのう何食べた?」は家族にも視点を向けていました。史郎の母親が、息子の恋愛傾向を必死に理解しようとするのですが、理解しきれない。その複雑な感情を、梶芽衣子さんが見事に演じていましたよね。LGBTに対しての世代の感覚の差をちゃんと描きつつ、食卓を通して温かくアットホームに収めていた。「おっさんずラブ」と双璧で、LGBTを明るく真摯に描いた素晴らしいドラマです。よくぞ平成ラストで、この2つの名ドラマが生まれたなと思います。
そして「3年A組―今から皆さんは、人質です―」。これは、特筆すべきでしょう。デジタルとの向き合い方が変わっていく、その危険性を最終回で大きくメッセージとして出していました。SNSでの安易なコメントや噂の拡散が人間の命を奪うこともあるのだと、菅田将暉さん演じる柊一颯が叫ぶ最終回は話題になりました。しかも、生徒の一人が「先生、あの事件で、世の中が大きく変わるなんて事は全然なく、まるで無かったかのようにみんなせわしなく生きて」と語るナレーションが入っていたんですね。ここがこのドラマの鋭いところで、まさに、実際の社会はなにも変わっていない。「3年A組」が話題になり、視聴者は一瞬SNSに対して危機感を覚えたかもしれない。けれど、すっかり忘れて同じ繰り返しになっています。2019年は芸能界でもいろいろありましたが、そのたび、いろんな人がSNS、しかも匿名であらゆる方向からネタをつつき出し騒ぎ話題になります。でも本質的に変えなければいけないことはミリ単位も動いていないのではないか、と思うことが多くありました。「3年A組」はそれさえも描いていたんじゃないかと思います。すごいドラマでしたね。
「3年A組」の次クールに、「向かいのバズる家族」もあり、こちらも家族の視点からSNSの問題を提示していました。SNSが、悩まなくていいことを大きな悩みに膨らませてしまう危険な種になっているのは事実。これから、もっとしっかりと描く必要があるテーマだと思っています。もちろん、実際に悩んでいる人ほど「ドラマでまで、そんなトラブルをリアルに見たくない」と拒否反応を起こすかもしれません。ただ、フィクションという形だから描ける解決方法の提案があるし、ネットと隣接したメディアのテレビだからこそ、注意喚起できることがある。「3年A組」でも、ラスト「変わることなんて全然なく」としながらも、さらに「先生から教わって、学んで、考えるようになった」と続くんですよね。生徒たちは確かに変化していた。少しは変わるかもしれないと信じて動くことの救いというか、声をあげることは決して無駄ではないというテーマを感じました。
働き方改革に向けての新たな提案「わたし、定時で帰ります。」「ハケン占い師アタル」
―平成31年は、働き方改革をテーマにしたドラマも多かったですね。「わたし、定時で帰ります。」も話題になりました。
「わたし、定時で帰ります。」は、私の平成31年のナンバーワンです! いろいろと発見があって面白かったですね。ソフトウェア会社に勤める吉高由里子さん演じる東山結衣の元恋人で、どんなハードで無茶な条件の仕事も完璧にこなす種田晃太郎役の向井理さんが絶賛の嵐でした。ここで注目したのは、種田の設定がワーカホリックということなんですよ。結衣の恋人で、デートの時間もちゃんと割いて、料理もできて、彼女の仕事にも理解があって…という、中丸雄一さん演じる諏訪巧より、種田に支持が集まったのが興味深かったです。プライベートを犠牲にしてでも、働いてチームに貢献する姿に美徳を感じる人は、まだまだいる。働き方改革が浸透するのはもう少し先かな、と思いました。
そもそも「わたし、定時で帰ります。」とタイトルがついてドラマになることが、日本の働き方の現状を表していますよね。「わたし残業しちゃいました」というタイトルがつき、「そりゃすごい、残業するなんて!」と視聴者が注目するくらいになってやっと、働き方が変わったと言えるんじゃないかな(笑)。ただ、私自身は残業まみれを推奨していないという前提で、一点付け加えておきたいのは、残業する人全員がワーカホリックではないということです。仕事が大好きで、時間関係なくやっていたい! という、エクストリーム・ワーカーもいる。残業「させられている」のではなく「大好きだからしている」というその差も、これからドラマに細かに描かれるべきかもしれません。
―なるほど。仕事が好きだからやる、という人との違いは、確かにありますね。残業や働き方のドラマといえば「ハケン占い師アタル」もそうでした。
杉咲花さんは新時代のトップを走る俳優さんですよね。小動物のような可愛さの奥に見える、どっしりとした風格は末恐ろしいくらいです。彼女の演じるアタルも素晴らしかったですし、このドラマで私がもう一人感心したのは、上司の大崎を演じた板谷由夏さん。オドオドしつつも、ちゃんと周りを考えて、グループを束ねているその存在感が、まさに「今の時代のリーダー」でした。それまでは姐御肌のイメージが強かったので、こんな弱さを滲み出す芝居もできるんだ、と驚きました。「ハケン占い師アタル」のテーマはかなり重いものだったですが、板谷さんの母性が、ドラマをやさしく、そして柔らかくしていたと思います。
令和元年のドラマは「人間関係と心の奥深く」がテーマ
―令和のドラマに関しても、少し感想を。2019年夏クール(7月から9月)のドラマはいかがでしたか。
平成の終わりには社会的なドラマが多かったですが、令和に入ってからの7月から9月枠は人の心のひだをしっかりと見つめた名作が出ましたね。「凪のお暇」「セミオトコ」「これは経費で落ちません!」…。どれもある意味お仕事ドラマなんですが、システムや働き方そのものではなく、人間のつながりに焦点が置かれていました。
印象的だったのは「セミオトコ」。脚本は岡田惠和さんです。NHK連続テレビ小説の「ひよっこ」もそうでしたが、彼の描くドラマには、ひとつの場所に、登場人物が集まる団らんのシーンがあるんです。「セミオトコ」も、うつせみ荘のみんながリビングに集まって自分の考え方や生き方を語る。見ていて本当に幸せなドラマでした。岡田さんのインタビュー記事で「『セミオトコ』はめっちゃ苦しんでいて、1話書き終わるごとにボロボロになっています」とあって、その苦しみから、あんなに穏やかで和やかで美しい会話が誕生するんだな、と胸がいっぱいになりましたね。
―10月からの注目ドラマについて教えてください。
たくさんあり過ぎて迷います! やはり岡田さん脚本の「少年寅次郎」は要チェックですね。あと、ドラマ「きのう何食べた?」「サギデカ」などを見て、最近ノリに乗ってるなと感じる脚本家・安達奈緒子さんの「G線上のあなたと私」も楽しみです。そしてもう一作品。賀来賢人さんが主演する「ニッポンノワール ―刑事Yの反乱―」。これは、面白い試みですね。先ほど語った2019年の名ドラマ「3年A組―今から皆さんは、人質です―」と同じ制作チームが手がけます。しかも舞台を「3年A組」のたてこもり事件から半年後に設定し、キャスト3人が同名同役として登場するなど、世界観をリンクさせているんですよ。脚本家の武藤将吾さんは、「電車男」もそうでしたが、時代の移り変わりを切り取って描くのがとても上手です。今回もどう新時代を捉え、問題提起をしてくるのか楽しみです。
若い感性に道を譲るという課題
また、一部の局では若返りを意識し、放送業界に入って数年の若者に大きなチャンスを与えてドラマづくりをする傾向も見られます。これは本当にいい動きだと思います。私は様々なメディアで、「世代交代が大事」と発信しています。演者も作り手もそう。もちろんそれは、ベテランをないがしろにするという意味とは全く違います。経験を重ねて、実体験で知っている人だからこそ、描けるドラマもある。70歳を超えて「まだまだ若い、まだまだ現役」いう人が大勢いらっしゃるのは素晴らしいことでもあるのですが、今の若者はそれを押しのけていこうとしない、やさしい世代なんです。けれど、若者が作るからこそ訴求できるエンタメがあるのも事実です。恋愛ドラマは特にそうで、ベテランが過去の恋愛を掘り起こす、もしくはアンケートを取って情報を仕入れて作れば、技術は伴っているのでそれなりに成立はするでしょう。ただ、どうしても違和感が出てくるものです。若い感覚に任せるべきところはちゃんと任せる。これからの社会、それが理想だと思います。新しいものがすべて御馳走とは言いませんが、新たなクリエイターや演者たちがどんどん才能を発揮できるように環境を整えるべきです。ベテラン勢が煽り運転をしてはいけません…、すいません、これもオヤジギャグですね(汗)。
―いえいえ、キレイにまとまりました(笑)! 最後に、この回で平成30年…いえ、31年分、全てを通して振り返りましたが、いかがでしたか。
ひとつの時代を俯瞰で捉えることで見えてくることがあるのだと、私自身気づくことのできた連載でした。正直、めぼしいドラマをピックアップするのに苦労する年もありましたし、逆にまだまだ語りたい! という年もあって、1年の波って不思議だな、と。メディアは「今」を扱い、時代を映す鏡でもあるのですが、いつまでも語り継ぎたいものと、終わった瞬間忘れてしまうものは、月日が経たないと分からないですね。終わった途端に内容もキャストもぼんやりしか思い出せない花火のようなドラマもありますが、それはそれで愛しくて。今回、「ああ、私はあのとき、あの作品の何気ないシーンに救われたんだった」と思い出し、改めて胸を熱くすることができました。令和という新時代のエンタメを考える道にも通じる貴重な機会をいただき、本当にありがとうございました。

【著者プロフィール】影山貴彦(かげやまたかひこ)同志社女子大学 メディア創造学科教授。元毎日放送プロデューサー(「MBSヤングタウン」など)。早稲田大学政経学部卒、ABCラジオ番組審議会委員長、上方漫才大賞審査員、GAORA番組審議委員、日本笑い学会理事。著書に「テレビドラマでわかる平成社会風俗史」(実業之日本社)、「テレビのゆくえ」(世界思想社)など。
【インタビュアー】田中稲/ライター。昭和歌謡、都市伝説、刑事ドラマ、世代研究、懐かしのアイドルを中心に執筆。「昭和歌謡[出る単]1008語」(誠文堂新光社)。CREA WEBにて「田中稲の勝手に再ブーム」連載。
関西ウォーカー
この記事の画像一覧(全2枚)
キーワード
テーマWalker
テーマ別特集をチェック
季節特集
季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介
全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!
全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!
おでかけ特集
今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け
キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介







