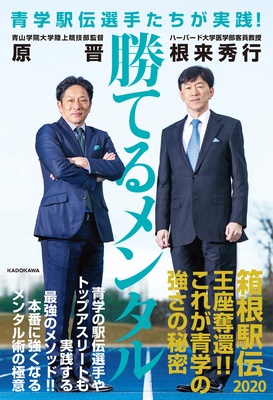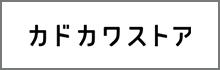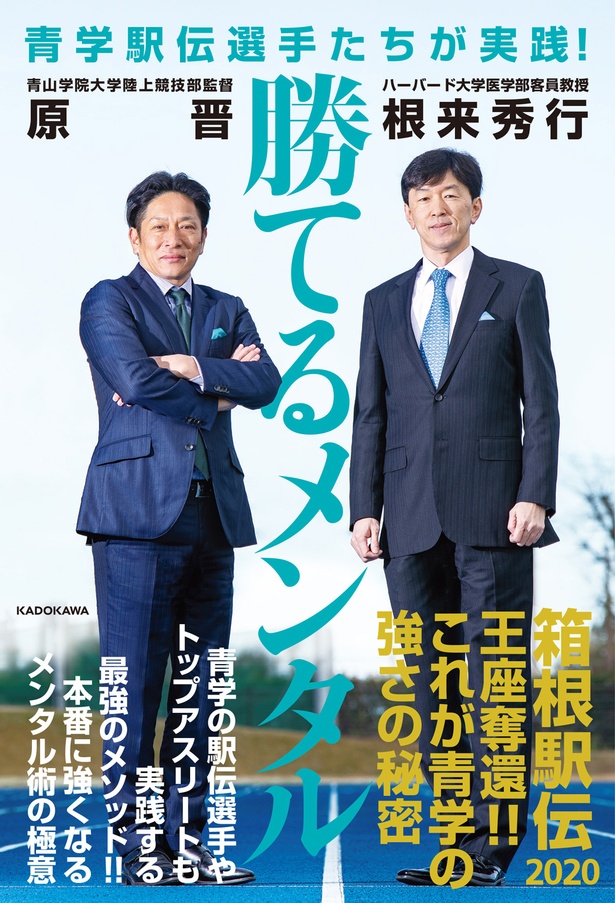箱根駅伝2020で王座奪還!! 青学の原監督が語る、アスリートに必要なメンタルとは
東京ウォーカー(全国版)
箱根駅伝2019でみせた復路スタート時点で5分30秒差という局面から、驚異の追い上げで復路大会新記録を叩き出すというドラマチックな展開。そして、翌年の箱根駅伝2020ではスローガンを「やっぱり大作戦」と銘打ち、見事総合優勝を果たした青学。彼らの力走に感動した人も多いはず。
そんな青学のあの強さの秘密について、原監督はこう話す。

【 体から立ち上がる「表現」】
いろいろな方から、こんな誉め言葉を頂戴します。
「青学の選手たちは、大人と話ができるし、とても好感が持てますね」
私としても、とてもうれしい言葉です。それも私が言葉にこだわって指導してきたからかな、と思います。
高校生を勧誘するにあたっても、私は高校生なりにしっかりと話せるかどうかを見極めているつもりです。自分から言葉で表現したいことがあるかどうか。そして大学に入ってからは、朝食の席での「1分間スピーチ」や、1か月に1度の「目標管理ミーティング」などを通して、選手に話すこと、考えることを重視してきた結果だと思います。
単純な言葉ですが、陸上競技の指導を通じて、明るく、前向きな人材を青山学院大から世の中に送り出したいと思っているのです。
そして私は、強い、速い選手よりも、試合直前になると生き生きしてくる選手が好きなのです。
試合は、学生にとっての発表会の場です。大切な試合が近づいてくると、そうした選手たちは体が締まり、走っているときも腰の位置が高くなり、表情もすごく生き生きしてきます。体つきだけを見ても、「これは状態が上がってきたなあ」というのが分かり、選手からオーラが不思議と立ち上がってくるのです。
思い返すだけでも、神野大地、久保田和真、そして森田歩希や林奎介といった選手たちからはポジティブなオーラが出ていたのを思い出します。2019年度のキャプテン、鈴木塁人もこの列に加わってきます。
こうした選手たちは、試合開始5分前になると、もう自分の力を表現したくて仕方がないタイプの選手たちです。試合が近づけば近づくほど、表情がにこにこしてきて、集中力がグッと高まってくる。きっと、厳しいなかにも余裕があるのでしょう。
一方で、試合前になると、逆にムードが沈滞してしまう選手もいるにはいます。実績のない選手、大舞台の経験のない選手だと、試合が近づいてくるにつれて、不安が隠しきれなくなってきます。
これは科学的にはなかなか証明できないことだと思いますが、不安がなにか体に影響を与えるのかと考えざるを得ないのです。
箱根駅伝を勝つには、データが大きな意味を持ちます。私は4連覇の数値をデータ化することで改めていろいろな学びを得ました。しかし選手の雰囲気や、体つきを見て感じることが、最終的には勝敗に直結してくるのです。これが勝負事の面白さでもあるのですが。

【 上級生と下級生のメンタルの強さの違い 】
ただし、そのオーラというものは素質、持って生まれたものとは限りません。
学生の場合は、学年に従って成長するものです。
私の指導経験からすると、下級生のメンタルと、上級生のメンタルでは「地力」や「ベース」の力がまったく違います。
2018年度を例にとれば、森田主将をはじめ、橋詰大慧、梶谷瑠哉、小野田勇次、そして林といった面々は心身ともにしっかりしていて、信頼できる選手たちです。
それはこの学年が特別だったのかもしれませんが、それでも大学で4年目を迎えるとなれば競技会での経験もたっぷりと積んで百戦錬磨、ケガ、人間関係などの苦労も味わい、総合的に強くなっていく。
私が見ていると、彼らは決してレースだけでメンタルが強くなったのではなく、日々の責任感からメンタルが安定し、勝てるメンタリティを獲得したのかな、と思い至ります。
ただし、競技の経験を積んだから強くなるというのは間違いです。彼らは、監督である私と戦い、下級生に模範を示すという重責に晒されています。つまり、会社でいえば、常に中間管理職の役目を果たしてきたのが4年生です。
強くなる要素というのはトラックやロードのなかばかりではなく、生活のなかにもあるのです。4年生は、走りや寮生活のなかでチーム全体を束ねていかなければならず、しかも失敗は許されない。つまり、下級生を前にして、模範とならなければいけない。特に2018年度の青学大は、選考レースやポイント練習でひとつでも失敗したらメンバーから漏れる危険性がありましたから、緊張感から解放されることはなかったでしょう。
これは陸上競技に限らないとは思いますが、大学スポーツでは、4年生は勝負するために自分を律し、日々結果を出し続けられることが必要で、常に生活のなかから勝負していく。だからこそ、レースでも責任感を持って走ってくれると信じられる。
下級生とはそのあたりに差が出るような気がします。下級生は4年生の傘の下で庇護されている。様々なプレッシャーとの戦いは上級生が全部引き受けてくれているのに、下級生はそれだけの恩恵を受けていることに、なかなか気づけないわけです。
知らず知らずのうちに、恵まれた環境で走っていると、いざレースで厳しい局面に遭遇すると、地力や能力、そして精神力の差があぶりだされてしまう。
それを考えると、私の方もこれからは下級生に関しては、きめの細かいフォローをしなければいけないと気づかされました。
たとえ同じ練習メニューを全員がこなしたとしても、中身は違うのだということを認識しなければいけないのだな、と痛感しました。
陸上は科学です。練習の結果、成果はレースに直結します。だからこそ、同じ練習をして、設定タイム通りにしっかりと走ったのならば、誰を起用しても同じような結果が期待できるはずです。ところが、実際には練習を経て得られた中身には、違いが生まれていたのです。
2018年度のチームは、上位を4年生が占めていました。集団練習のなかで、4年生が上位の3分の2を占めていたら、下級生は4年生の背中を見て走ればいいわけで、引っ張ってもらっているので、集団からは離れない。下級生たちも「4年生についていけば強くなれる」と信じているし、その気持ちのおかげで強くなっていく。4年生のおかげで、全員が高いレベルで走り切れるわけです。
では、同じタイムで走れた全員が同じ力を持っているかというとそうではなく、集団を引っ張る4年生の地力というものは、相当強かったというわけです。
私が、最強のチームは作れなかったけれど、「最強の4年生」は作れたかな、と思うのはこうした理由からです。
アイドルグループを例にとると、より分かりやすいかもしれません。紅白歌合戦のステージを見ると、メンバー全員が輝いて見えます。でも、私はこう思うのです。グループのトップメンバーが高いレベルのパフォーマンスを発揮して、ステージ経験が少なく、実力的には下のメンバーの力を引き上げているのではないか――。青学大を指導して、そうしたことを感じたりもします。
今回紹介したメンタルに関するメソッドのほか、「青学のメンタル強化の取組み」、「駅伝に必要なメンタル」、そして「具体的なトレーニング術」など、青学の原監督とハーバード大の根来教授の共著本『青学駅伝選手たちが実践!! 勝てるメンタル』(KADOKAWA)では、本番に強くなるメンタル術の極意を紹介しています。こちらもぜひ読んでみてください。
大澤政紀