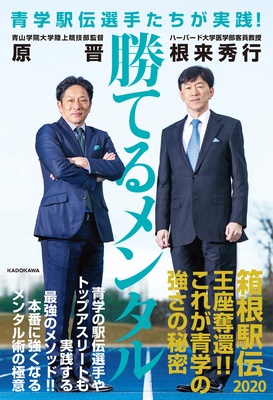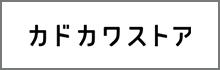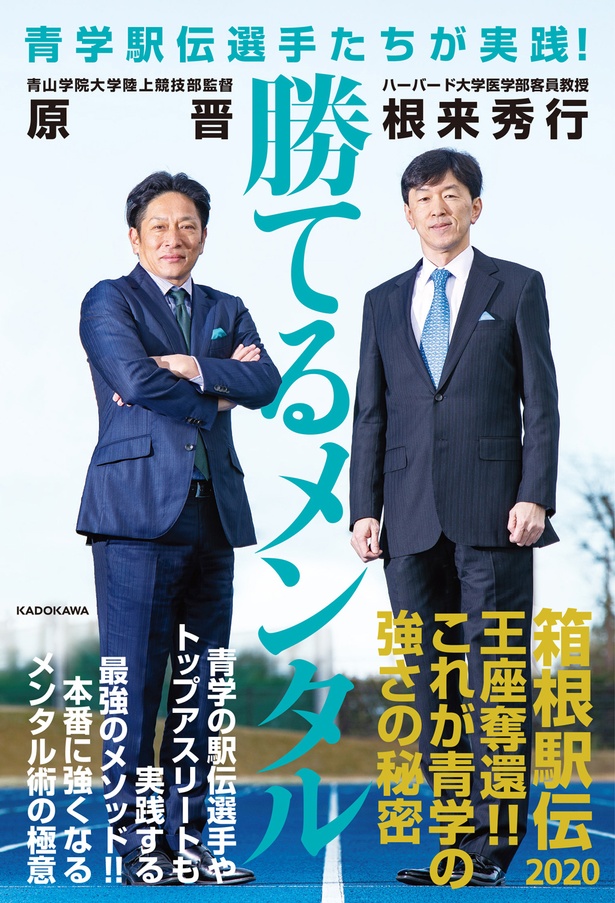箱根駅伝2020で王座奪還!! 原監督が語る「進化する姿勢」
東京ウォーカー(全国版)

箱根駅伝2020で王座奪還した青山学院大学。『ダメダメ世代』と呼ばれていた4年生が選手たちを『最高の世代』へと変身させた青学の原監督は、箱根駅伝について「もはや、監督という『個人商店』で勝てる時代ではない」と話す。そして今の青学の強みは『専門分野の集合体』だと話す。
2017年度のシーズンから、科学的なメソッドで青学に協力しているハーバード大の根来教授と原監督の対談の一部をご紹介します。
■選手が主体的になるためには

原 箱根駅伝はもはや、監督という〝個人商店〞で勝てる時代ではないんです。今の青山学院大の強みは「専門分野の集合体」ということだと思っています。それが強化現場に直結する仕組みを作ったんです。私だけの知識や経験だけでは絶対に勝てませんし、私だけのチームでもない。今の青学には、根来先生という医学のエキスパートがいるし、フィジカルトレーニングの分野では、中野ジェームズ修一さんというトップのフィジカルトレーナーがいて、「青トレ」を浸透させた。青学がフィジカルを重視したことで、他の大学も真剣に取り組むようになり、それが全体のレベルを上げたと私は信じています。それも私が呼んできて「さあ、やれ!」という支配型の構造ではなくて、私の仕事はナンバーワンの人を呼んでくる「プロフェッショナルの集合体」を作ることでした。
―――根来先生をお招きしたときは、どんな形で学生に話をしたんですか。
原 世界でも最新鋭の学びの場なんだよ、という話をしてお迎えしました。医学の最先端にいて、我々にはないノウハウを持っているというアプローチですね。
根来 私も初めて監督にお会いしたときに、そうした気持ちが伝わってきたので、だからこそ一緒に仕事がしたいと思ったわけです。私も自分が蓄積してきたものを選手たちに押し付けるつもりはまったくありませんし、いいところがあれば吸収してほしいと思ったわけです。
原 それこそがナンバーワンの方の発想だと思いますね。ただし、学生に学ぶ姿勢がなければ先生の時間を無駄にしてしまいかねませんし、そうした積極的な学生を育てるのが私の仕事だと思っています。
根来 「ナンバーワン」を取り入れるという発想、すごくいいと思います。しかも「こういう人を連れてきたから」とトップダウンで強要することはなく、選手たちは私と個人的な関係を築いて積極的に取り組んでくれましたから。2019年度のキャプテンになった鈴木塁人選手はとても好奇心が旺盛で、かなりメールのやり取りもしましたし、それこそハーバードの学生と同じレベルの好奇心の旺盛さを感じました。競技力は学生としてはトップレベルでしょうが、それにプラスして発想の柔軟性があり、そうした力が最前線で活躍されている理由だと思いましたね。
原 「泳がす」って大切なことだと思っているんです。もしも、私が鈴木にああせい、こうせいと言っていたとしたら、根来先生とのそうした関係は築けなかったと思います。いま、根来先生の話を伺って、鈴木が駅伝で強いというのは、好奇心が旺盛だからと気づきました。試合の日に向かって自分を上向きにしていくためにはどうしたらいいのか、それを自分のなかで培っているからなんですね。
根来 鈴木選手の場合は、間違いなくそうした感覚が養われているでしょうね。
原 それが可能になるのは、手前味噌になるけれども、私が答えを先に与えないからだと思うんです。ああしろ、こうしろではイエスマンばかりが育って、対応力がなくなる。やはり、勝つメンタルを育てるために必要なのは「問いかけ」ですよ。問いかけ的なアドバイスをすることで、選手が自分から欲を出して何かを得ようとする発想になってくる。主体的に動くことが、考える力を養いますからね。
―――あえて、泳がせる。
原 最近、私が感じていることは、生徒や子どもが悪いこと、ルール違反をしたとする。これに対して、熱意がある教育者ほど全力で対応しがちなんです。これ、いいように見えて実は良くない。もっと、泳がせる余裕があった方がいいと感じるんです。
―――全力で対応してはいけないということなんですか。泳がせるというのは。
原 人命や人権に関わるトラブルであれば、全力で対応する必要があるし、時には真剣に怒る必要があるでしょう。しかし、別種の些細なトラブルと同じような「圧」で怒ったり、それこそ「どうして根来先生のところに行ってないんだ!」と怒鳴っていては、選手や学生は疲れてしまいます。こういうことは泳がせた方がいいと思ってるんです。
根来 そういうアプローチをされてしまうと、学生は息が詰まってしまうし、考える力が失われてしまいますね。
原 だからこそ、私は学生を泳がせて、学生が根来先生と一緒になって、何かを見つけてほしかったんです。ただし、世の中の「青学が強いのは、原監督の指導方針がいいからなんだろう」という風潮が支配的になるのは、それもまた怖いなと思ってるんです。私には私の指導理念、スタイルがあって、他のチームには他のチームのメソッドがあるべきでしょう。私が今欲しているのは、「メソッドの戦い」なんです。各校がバチバチやり合ってこそ、日本の陸上界が盛り上がっていく。日本の陸上界を見ていると、学閥による先輩後輩の関係が重視されていて、独自のアイデアの発展が阻害されている気がするんです。それじゃ、「勝てるメンタル」になれるわけがない。だって、先輩後輩の序列は一生変わらないものね(笑)。
根来 実は、医学界も同じような問題を抱えているんです。
原 医学の世界でもそうなんですか!
根来 日本の医学界は教授中心のピラミッドで、だいたい自分の大学の後輩で固めていく感じです。ハーバード大学では、日本人である私を招いてくれたりだとか、外部の発想をどんどん取り入れて活性化することを積極的にやっています。私の経験からすると、異端だからこそいろいろな意見が言えるわけで、そこから業界が変わるのであって、監督の言う通り派閥のなかで動いていては、発想の角度が変わらないと思うんですよ。
原 ハーバードでは派閥という存在はないんですか。
根来 多少はありますが、派閥が間違った方向に向かわないように新しい人を入れて新陳代謝を促しますね。そうすると、過去の成功にあぐらをかいてはいられなくなります。
原 グループ、そして個人が進化するわけですか。
根来 その通りです。原監督は「進化する姿勢を止めてしまうと退化が始まる」とおっしゃいましたが、アカデミズムの世界でも保守に回った瞬間、勝つメンタルからは遠ざかってしまいますね。長年、研究者としてトップにいる人は、自分の研究室に新しい風を入れたり、あるいは斬新な発想を持っている人を自分と同格で招いたりするんです。
今回紹介した対談の全貌ほか、「青学のメンタル強化の取組み」、「駅伝に必要なメンタル」、そして呼吸や自律神経など「科学的にメンタルを強化する術」など、青学の原監督とハーバード大の根来教授の共著本『青学駅伝選手たちが実践!! 勝てるメンタル』(KADOKAWA)では、本番に強くなるメンタル術の極意を紹介しています。こちらもぜひ読んでみてください。
非科学的な指導を排除して、科学的な裏付けをもって選手を指導する。メンタルは鍛えるものではなく、あやつるものであり、そのスキルが存在する。「こういうことを10代のうちに知っていれば、人生が変わったのに」と思う事柄ばかりですが、様々な年齢層の方に多くのヒントとなるはずです。
大澤政紀