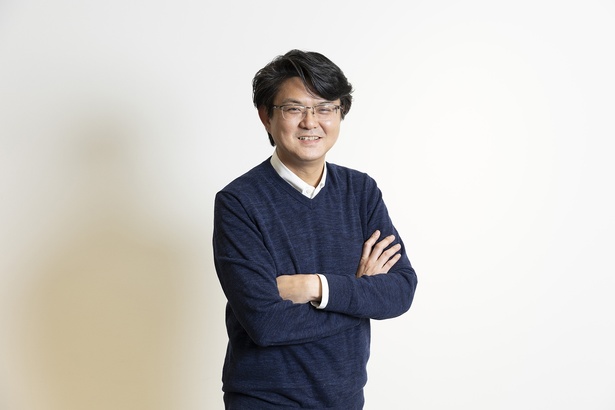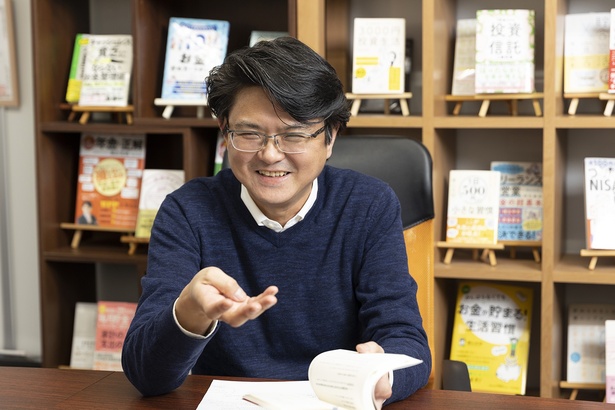FP横山光昭のお金の悩みがなくなる資産形成プラン。「収入」と「所得」の違いを知ることからはじまる、サラリーマンのための節税法
東京ウォーカー(全国版)

「脱税」ではなく、あくまでも「節税」ということを意識する
サラリーマンが利用しやすい4つ目の所得控除が、「医療費控除」。自分や家族の医療費を支払ったときは、その金額から保険で補填した金額と所得金額の5%を差し引いた金額を、医療費控除として所得金額から差し引くことができます。
また、この医療費控除とは別に、「医療費控除の特例(セルフメディケーション特例)」という制度もあります。これは、医薬品を年間1万2000円以上購入した場合、その購入額が所得控除の対象になる制度です。
ただし、セルフメディケーション税制の対象となるのはすべての医薬品というわけではありません。ただ、胃薬や湿布などそれこそ日常的に使う有名な医薬品も数多く対象となっていますから、自分や家族のためによく医薬品を買う人にとっては利用しやすい制度です。対象となる医薬品には、「セルフメディケーション税控除対象」というマークがありますから、医薬品を購入するときにはチェックしてみましょう。
最後の「住宅ローン控除」は、ローンを利用して住宅を購入した場合に、年末時点での住宅ローン残高の0.7%が、入居時から最長13年間にわたって控除される制度です。若い人の場合、すでに住宅を買ったという人は多くないかもしれませんが、今後のためにも知っておいたほうがいい制度であることは間違いありません。
ここまで、サラリーマンにも実践しやすい節税法について解説してきました。しかし、注意してほしいのは、あくまでも「節税」である点です。法律に反して「脱税」してしまえば、犯罪を犯したことになるからです。
もちろん、「なるべくたくさん税金を払いたい」という人はいないでしょう。でも、税金は私たちが生きる社会をよりよくしていくために欠かせないものです。極端な話をすると、税金という制度がなくなってしまえば、急病のときに救急車を呼ぶにもお金を支払わなくなるなど、今あたりまえのように享受している公共サービスも受けられなくなります。そう考えて、定められた制度をうまく利用し、法律の範囲でかしこく節税することを考えてほしいと思います。
この記事のひときわ
#やくにたつ
・いかに課税所得を抑えるかが節税のポイント<br />・定められた制度をうまく利用し、法律の範囲でかしこく節税する
構成=岩川悟(合同会社スリップストリーム)、取材・文=清家茂樹、撮影=藤巻祐介
この記事の画像一覧(全4枚)
キーワード
- カテゴリ:
- タグ:
- 地域名:
テーマWalker
テーマ別特集をチェック
季節特集
季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介
全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!
全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!
おでかけ特集
今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け
キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介