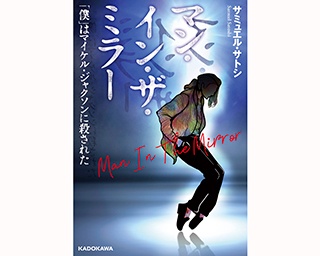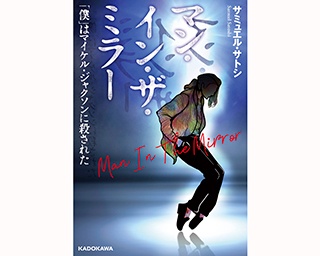『マン・イン・ザ・ミラー』連載 第35話
東京ウォーカー(全国版)

MJ-Soul活動休止の報せは瞬く間に広がった。
惜しむ声は多く、最後のライブを見届けようと吉祥寺の『サンタバーバラ・カフェ』にはたくさんのファンが詰めかけた。
コングくんはまだ納得いってない様子だったが、このまま一緒に続けたとしてもお互いもっと傷つけ合うことになりそうで、ひとまず僕が納得できるところまで、別々の道を歩むことにした。
ユーコとジュディスにそう伝えると淋しそうな顔をしたが、なんとなく前々からこうなることが分かっていたようで、すぐに受け入れてくれた。
久しぶりに一緒に踊ろうとフレディーにも声をかけたら、二つ返事で来てくれた。今はクイーンのインパーソネーターとして都内各所で大活躍している。もっとも、本人はそれを“なりきりパファーマー”と呼んでいるそうだが。
嬉しかったのは、フレディーが「どうせなら、オパちゃんも呼ぼうよ」と言ってくれたことだ。あの横領嫌疑の「以上!」事件以来、二人がギクシャクしていたのは誰の目から見ても明らかだったので、まさかフレディーからそんな発言が出るとは思ってみもなかった。オパちゃんは長いこと一線を離れていたが、声をかけたら短く「やる」と言って参加してくれた。
図らずも、僕らはオリジナルメンバーで活動休止のライブをやることになった。
当日はリハーサルから楽しかった。誰一人まともに踊らず、思い出の『ザ・ウェイ・ユー・メイク・ミー・フィール』では、おどけてみんなでふざけ合った。懐かしかった。それぞれが収まるところに収まったような、とてもフィットしていて居心地がよく、まるで安田ビルの前で踊っているような感覚だった。
ユーコがいつのものようにフレディーに突っ込む。
「ちょっと! フレディー! 胸毛、出し過ぎだって!! しかも、なんでTシャツ、乳首のとこだけ穴開けてんの!! キモい!!」
「『愛という名の欲望』のときのフレディーだ!」
「それ、マイケルと関係ないし!!」
するとジュディスが「Crazy!!!」と言って目を覆った。オパちゃんは相変わらず我関せず、一人寡黙に開脚している。コングくんはすっかり黒人メイクになって目だけがステージに浮かんでいる。
誰もが肩肘を張らず、和やかで、終始笑いが絶えなかった。もしかしたら僕はこの幸せを噛み締めることさえできれば良かったのかもしれない。
活動休止のライブというのは、案外ファンの淋しさとは裏腹に、やる方の心は穏やかなのだろう。これから失うものの大きさが人を素直にさせるのか、または一度は止まるきっかけができて、みんなどこかホッとしているのか。ただ、それをまた始めるとなると、そう簡単にはいかないことを誰もが知っている。
終演後にコングくんが舞台に上がってスピーチした。
「とても残念ですが…、僕らMJ-Soulは本日をもってしばらくの間、活動を休止します。今まで応援してくれたみなさん、本当にありがとうございました。最後に僕から一つだけ、ここにいる皆さんにどうしても伝えておきたいことがあります。よくマイケルが亡くなって一つの時代が終わったなんて言葉を決まり文句のように耳にしますが、そんな簡単にマイケルの時代が終わるものでしょうか。そんなものじゃないはずです、マイケルは。だって、マイケル・ジャクソンですよ! 誰だと思ってるんですか! それと同じように、MJ-Soulも僕は終わらないと思っています。イーくんはこれからもソロでマイケルの魅力を伝えていってくれますし。僕らも、ここにいるみんなも、一緒に成長していってそれぞれのやり方でマイケルを伝えていきましょう! いつかまた必ず活動を再開したいと思います。そのときは東京ドームで! 本日はお越しいただきありがとうございました!」
場内に笑いと温かい拍手が起こる。
今日のライブが楽しかっただけに、僕は自分の選択が正しかったのか改めて考えていた。ただ一つハッキリしているのは、みんなマイケルに対する愛は一緒だということだ。そのやり方がちょっと違うだけで、僕らはマイケルのことが大好きなのだ。
そして僕はまた、始めたころのように一人になった。
#HISTORY
ソロになってからもオファーの数は減ることなく、ひっきりなしに出演依頼がきた。
僕はある程度ステージの広さが確保できて、なるべくきちんと照明があるところ、音響システムの良いところ、そしてマイケルになるためのメイク室が最低限もらえるところを選ぶようにした。
また、以前のようにただ闇雲にイベントに出るのではなく、オーガナイザーと事前に打ち合わせをして、主旨を聞いてから、志と質の高いところだけに参加するようにした。なぜならその方が僕も気持ちが入るからだ。
そんな風に仕事を選び始めると「イーくんは変わった」とか「お高くとまっている」とか、中傷してくる人が同業者で増えてきた。でも僕は普段定職についていて、これ一本で食べていこうとはもう考えていないので好きにマイケルを追求させて欲しかった。
未だに世間は、インパーソネーターはモノマネショーと一緒で、何か面白いことをやる芸人として認識している人が多い。こっちがきちんと基準を作らなければ、木箱の上など、どんどん劣悪なところでやらされて、見せ物で終わってしまうことがあるのが辛かった。いい加減、パフォーマンスする前にクスクスと笑いが起きる空気を変えたかった。
そして僕は自分の理想を突き詰めるために、ソロのワンマンも年に一回だけ行うようにした。バックダンサーや競演相手はその都度、楽曲に応じて選出している。さすがにSHIBUYA-AXのような規模ではできないが、あれ以来、想像を働かせて表現する喜びを知ってしまい、とうとうマイケルの未発表曲にまで手をつけるようになった。
まるで禁断の実をかじるように、もしマイケルが生きていればどんな演出や振り付けをしていたのだろうかと妄想を膨らませ、僕は神の領域に足を踏み込むようになった。
その代償は思いのほか大きく、公演後の疲弊は凄まじかった。毎回体が硬直し、お腹を下してボロボロになった。ただ、どれほどクオリティの高さを極限まで突き詰めたとしても、一部の好事家以外、全体的な反応は今ひとつなのがもどかしかった。自分の情熱とファンの理解がなかなかかみ合わず、僕は一人迷走していた。
そんなときだった、あの一言を言われたのは。
マイケルの名曲を凄腕の生バンドが演奏し、そこにダンスでセッションするというオファーは、とても画期的で久しぶりに食指が動く話だった。
今までバンドでやった経験などほとんどなかった僕に、これは新たな可能性に挑戦できるまたとないチャンスだと思った。マイケルの曲をバンドサウンドで踊ることができたらどれほど気持ちがいいだろう。僕はしつこいぐらい何度もオーガナイザーの人と会って綿密な打ち合わせをした。
「このセッションは本当アーティスト冥利に尽きます! たとえばこんな流れはどうですか? ここは『ロック・ウィズ・ユー』より、得意の『ビリー・ジーン』にして、暗転したあとは『スリラー』の方が僕のファンが喜ぶと思うんですよね」
嬉々としながら自分から色々と提案していると、突然、オーガナイザーが呆れたように息を吐いてこう言った。
「あのさ、一ついいかな。さっきから聞いてると、僕のファン、僕のファンって言うけどさ。言っとくけど、君のファンじゃないよ」
「え?」
「マイケルのファンだよ」
僕はオーガナイザーの態度が突然豹変したことにも驚いたが、自分が思わず無意識の内に口にしていた言葉を指摘されて視線がさまよった。
「それとね、君。時々会話のなかでアーティストって使うけど、自分のことアーティストだなんて言わない方がいいよ。アーティストって言うのはね、人から言われるもんであって、自分で言うもんじゃないから」
何も言い返せずに、顔が熱くなって下を向いた。
「もっと謙虚になりなよ。君を見てると自意識過剰で気分が悪くなる。マイケルに似てさえいれば、君じゃなくても良かったんだよ」
そのとき、前にコングくんから言われた「これからはマイケルが凄いんじゃなくて、一斗くんが凄いからみんなついていくってならないとねって」という言葉が思い出された。
悔しかった。
黙っていることがまるで認めた証拠のようで、自分が惨めだった。
そして僕はとうとう、体が動かなくなってしまった。
(第36話へ続く)
同じまとめの記事をもっと読む
この記事の画像一覧(全1枚)
キーワード
テーマWalker
テーマ別特集をチェック
季節特集
季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介
全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!
おでかけ特集
今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け
キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介