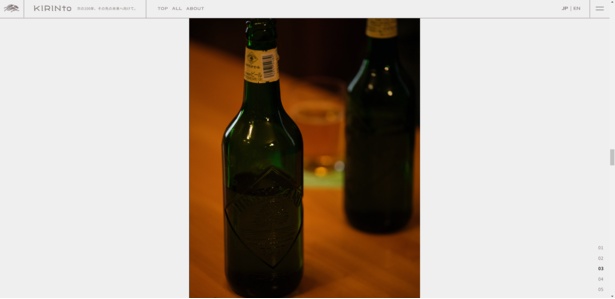1.5万人から支持される「KIRIN公式note」。今求められるオウンドメディアの役割とは
東京ウォーカー(全国版)
公式noteを開設して丸4年。今や1.5万人ものnoteフォロワー(2023年7月24日時点)を擁し、オウンドメディアの成功事例としてたびたび名前が挙がるのが、キリンホールディングス株式会社だ。ソーシャルメディアの特性を生かしたコミュニケーションを設計し、クリエイターとコラボレーションを行い、社内外を巻き込みながら共感の輪を広げていく。まるでお手本のようなオウンドメディア戦略を実現させた立役者、コーポレートコミュニケーション部の平山高敏さんにインタビューし、現在にいたるまでの過程や裏側に迫る。前編の本記事では、立ち上げの背景やnoteを発信の場に選んだ理由、社内におけるオウンドメディアの役割について話を聞いた。

社内で眠っているストーリーを発掘して発信。プラットフォームの利点に着目したメディア運営
ーーもともとはデジタルマーケティングを行う部署に所属していたとのことですが、オウンドメディアの立ち上げに挑むまでにどのような経緯があったのでしょうか?
【平山高敏】私が入社した2018年当時のキリンでは、ECサイト上でコラムやレシピなどのちょっとした読み物は掲載していたものの、今の公式noteでやっているような、いわゆる長尺でストーリーや想いを伝えるというコンテンツはありませんでした。転職してきて、ビールの造り手の方やCSV(※)といった非財務領域を推進する方と会話するなかで、「表に出てきていないだけで、社内にはおもしろい話がたくさんあるんだな」と感じたことが構想のきっかけでしたね。私自身、商品や取り組みの裏側を知ることで、キリンに対してより愛着がわいたというのがあったので、「これを外に向けて発信していくことは、理にかなってるのではないか」と考え始めました。しかしながら、いきなり大きくメディアを始めるのはイニシャルコストがかかりますし、社内的にもハードルが高い。そこで、目を付けたのがnoteでした。
※CSV…Creating Shared Valueの略。企業が社会問題に取り組むことで社会的価値を創造し、その結果、経済的価値も創造されること

【平山高敏】当時、気鋭のプラットフォームとして注目を集めていて、ちょうど企業向けのプランが始まったくらいのタイミングだったので、コンテンツさえ作ってしまえば、オウンドメディアを立ち上げられると思ったんです。ライトなTwitterや写真で見せるInstagramとはまた違う、noteという場所でなら、カルチャーやサステナビリティなどの文脈とともに、私たちが伝えたいストーリーや熱量が素直に伝わるんじゃないかなと考え、まずは始めてみることにしました。
ーー今でこそ、企業情報の発信の場としてnoteを選ぶ企業も少なくはありませんが、「KIRIN公式note」はそういった点では先駆け的な存在ですよね。
【平山高敏】社内から否定的な意見こそ挙がらなかったですが、比較的新しいプラットフォームだったということもあり、そもそもnote自体を知らない方も多かったですね。ストーリーを伝えやすい場であることに加えて、クリエイターやインフルエンサーとのリレーションを築くことができる、我々と一緒に発信してくれる人ができれば、共感の輪が広がっていくということを社内向けにプレゼンしました。
ーーnoteを活用することで得られたメリット、一方でデメリットや課題に感じている点はありますか?
【平山高敏】Twitterと相性のいいプラットフォームなのでSNS上の拡散力があり、ある程度しっかりと狙ってコンテンツを作れば多くの反響をいただける点は大きなメリットですね。また、サーバーの構築・保守にコストがかからないこと、note上でおすすめの記事としてピックアップされれば効率よく集客ができることも、noteならではのよさだと感じます。一方で、我々はあくまでnoteというデパートに出店している立場なので、プラットフォームそのものや訪れるユーザー層の変化による影響をダイレクトに受けてしまいます。「KIRIN公式note」は開設して5年目に突入しましたが、ユーザーの傾向によって刺さるコンテンツ、刺さらないコンテンツがまるで変わってしまうので、翻弄されやすいという点で難しさは感じますね。もともとはカルチャー思考が強い、ソーシャルイシューへの関心が高い層が多いだろうという見立てから、noteを発信の場に選んだところもあるので、そこが変わってくるのであれば、別の形でメディアを立ち上げるなどの発想も出てくるかもしれないですね。

テナントと旗艦店。2つのオウンドメディアを持ち、メッセージを発し続ける理由
ーー「公式note」と「KIRINto(キリント)」という2つのオウンドメディアをお持ちですが、それぞれのコンセプトや役割の違いについて教えてください。
【平山高敏】「公式note」は先ほどお話したように、noteというデパートにテナントとして出店しているような状態で、プラットフォームに依存しているという点でTwitterやInstagramと並ぶソーシャルメディアのひとつなんですよね。一方で「KIRINto」は、「kirin.co.jp」というキリンのドメインの中にあるサイトなので、いわば旗艦店のようなもの。社内における建て付けや立ち位置は決定的に違います。
【平山高敏】コンテンツ面では、「公式note」は比較的、若年層かつ、ソーシャルイシューに興味のある方に向けて、現在進行形で今まさに何らかの課題に向き合っている従業員を出していくような記事、クリエイターとのコラボを通してキリンの人格に触れてもらえるような記事を中心に置いています。「KIRINto」は、キリンの過去から未来を見渡したうえでのコンテンツ設計で、ゲストを招いて問いを立てていくような記事を置いています。“キリンの人格を知ってもらい、キリンに期待していただく”という意図は両者共通していますが、各メディアのターゲットはもちろん、発信するメッセージのニュアンスは変わってきますね。
ーーキリンの場合、ステークホルダーが多岐に渡りますが、メディアのターゲットやペルソナ設定はどれくらい作り込んでいるのでしょうか?
【平山高敏】ほぼ作り込まないですね。メディアの作り方としては間違っているかもしれないですが、変わる前提で大まかなターゲット像を作る程度にとどめていて、“今はこういう読者に刺さってほしい”という狙いを立ててコンテンツを制作しています。例えば、アルコール飲料と「iMUSE(イミューズ/免疫の維持をサポートする乳酸菌ドリンク)」のような機能性表示食品とでは、どう見てもターゲットが違うじゃないですか。実は、これをひとつのメディアの中でやらないといけない難しさがあって。ビールの記事、CSVの記事、健康食品の記事、これらの読者が一緒であるわけがないので、メディア全体の世界観というよりは、個別具体のコンテンツ設計を行って、コンテンツごとに設定したターゲットに刺さるか、クリエイターさんとコラボする場合はその先にいるファンにきちんと届くかといった点を重視しています。

【平山高敏】商材やステークホルダーが広い以上、メディアの色が薄まってしまうのは仕方がない部分もありますが、“noteらしさ”“KIRINtoらしさ”を出すためのトンマナや切り口を意識しつつ、コンテンツごとに最適化を図っているような状況ですね。
この記事の画像一覧(全7枚)
キーワード
テーマWalker
テーマ別特集をチェック
季節特集
季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介
全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!
全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!
おでかけ特集
今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け
キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介