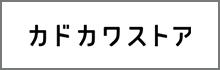品質で勝負をかけたい。宮城県のベンチャー酒蔵「一ノ蔵」の挑戦
東京ウォーカー(全国版)
酒造りに大切なのは、風土、米、水、そして人
一ノ蔵には農業部門『一ノ蔵農社』がある。きっかけは1993(平成5)年の冷害だった。前年に新しい蔵を建て、量を仕込めるようになったが、冷害で肝心の米がない。原料の大切さをあらためて痛感した。
契約栽培の農家と『松山町酒米研究会』を立ち上げ、特別栽培米をつくり始めた。農業試験所の役割も担い、栽培技術を蓄積し、情報提供も行っている。栽培できなくなった休耕田を一ノ蔵に任せたいという農家の申し出も増えてきた。
「大崎地域の農業は、2017年に世界農業遺産に認定されました。これからも農地をよりいっそう大切にしていきたいと考えています」と鈴木さんは話す。
「土を育て、風土を育てることが、よりよい酒につながっていくんです」。総杜氏の門脇さんも「土地の米の味わいを表現したい」と言う。

「宮城でつくった酒というだけでなく、米も水も空気も、そして人も、オール宮城でつくった酒で評価を受けたいと思っています」。
鈴木さんの想いも同じだ。
「人が育たないところに、よい酒はない。酒蔵に生まれた父たちからも、働いてくれる人たちは家族のように大切にしろと口を酸っぱくして言われました」。
一ノ蔵は2018年に宮城県で初めてユースエール認定を受けた。若者の採用や育成に積極的な企業に与えられる賞だ。「いわばホワイト企業のお墨付きをいただいたようなものです」と鈴木さんはおどけるが、時間は不規則、重労働も多い酒造りにおいて、画期的なことだ。
現在、常勤スタッフのほかに約40人の蔵人がいる。最盛期の冬から春にかけて、シフト制の24時間体制で作業にあたるが、その分閑散期にまとめて休みをとれるシステムを採用した。
一ノ蔵を見学すると、若い蔵人がイキイキと働く姿を目にすることができる。杜氏になりたい、酒造りを学びたいという若者があとを絶たない。一ノ蔵のマークは、人という文字が4つ集まってできている。人が挑戦し、人が支え合う。理念は次世代へとつながる。

※KADOKAWA刊『会いに行ける酒蔵ツーリズム 仙台・宮城』より
栗原祥光
この記事の画像一覧(全13枚)
キーワード
テーマWalker
テーマ別特集をチェック
季節特集
季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介
全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!
全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!
おでかけ特集
今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け
キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介