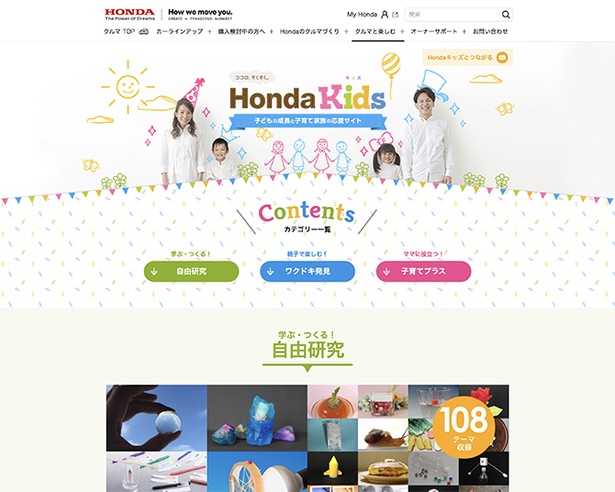「親子の挑戦と成長を支えるために」モビリティリゾートもてぎが“とにかく子どもに優しい”ワケ
東京ウォーカー(全国版)
“挑戦”と“成長”をテーマに掲げるテーマパークがある。それが、栃木県茂木町の自然の中に広がる「モビリティリゾートもてぎ」だ。モータースポーツの聖地として名を馳せるこの場所は、実は“子どもにやさしいテーマパーク”というもうひとつの顔を持つ。自然の豊かさ、里山の地形、ホンダモビリティランド株式会社の思想、そして家族のつながり。多くの要素が結びつき、同施設ならではの価値を形づくっている。

今回は総支配人の稲葉光臣さんに、施設の成り立ちや哲学、自然との向き合い方、地域連携、教育的意義、そして未来の展望まで、じっくり話を聞いた。
“子どもにやさしいテーマパーク”としての原点

――まず、モビリティリゾートもてぎがどういった施設か、あらためて教えてください。
【稲葉光臣】モビリティリゾートもてぎは、モータースポーツを核に持つ施設ですが、単なるレース観戦の場ではありません。子どもたちがチャレンジをすることで成長を感じられる、そんな場所でありたいと思ってつくられた場所です。チャレンジを通して「ああしたい」「こうしたい」と自分で考える“気づき”が生まれる。そのプロセスを後押しし、自ら考えて行動する力を育てることこそが、実はホンダの創業者・本田宗一郎さんがやってきたことの原点でもあるんです。私たちはその想いを、モビリティという手段を通して子どもたちに伝えていきたいと考えています。それは“結果を求める教育”とは違います。もっと自然に子どもたちが「これおもしろそう」と感じる瞬間をどう生み出すか。そのためには、楽しさとチャレンジ要素の“微妙なかけ算”のようなバランスが大事だと思っています。
【稲葉光臣】ホンダは、まだ高速道路が整備されていなかった時代に、鈴鹿サーキットをつくりました。その背景には、モータースポーツでクルマを鍛えると同時に、乗り物の楽しさを子どもたちに伝えるという目的もありました。そして、モビリティリゾートもてぎは、ホンダの創業50周年事業として誕生しました。次の時代を担う子どもたちに、ホンダが何を伝えられるかを考えたとき、挑戦、自発性、環境といったテーマが浮かび上がった。そうした発想から、この場所が生まれました。
【稲葉光臣】ホンダには「Power of Dreams」という言葉がありますが、その“どう夢を見るか”“どう能動的に考えるか”という精神こそが、私たちのコンセプトの中核にあります。
――この施設ならではの、特徴、魅力について教えてください。
【稲葉光臣】先ほど申し上げたように、子どもたちのチャレンジの場として、成長を促すというのはコンセプトの柱になっています。加えて、この立地の中にある“里山”という自然環境も大きな特徴です。その要素を、私たちが提供するアトラクションに取り込むことで、里山のおもしろさや大切さ、そして興味を持つきっかけを生み出すよう工夫しています。
【稲葉光臣】2017年にオープンした立体迷路の「迷宮森殿 ITADAKI」は、その代表的な例です。私自身も企画に携わりました。当時は立体迷路自体が珍しかったのですが、私たちは単なる構造物ではなく、生態系の5層構造を模したものにしようと考えました。一番上は猛禽類、その下には小動物や昆虫、さらに植物、そして最下層には土の中の細菌やミミズといった存在も含めました。2階からスタートする構造にして、普段目にする植物の世界から出発しながら、実はその下に支える世界があると気づけるようにしています。

【稲葉光臣】つまり、子どもたちが小動物になったつもりで知恵を絞って迷路を進み、なんとか生き延びてゴールを目指す。そんなストーリー性を持たせたアトラクションです。「森感覚アスレチックDOKIDOKI」や屋内ネット施設「巨大ネットの森 SUMIKA」も同様に、自然の構造や人と自然の関係性を取り込んで設計しています。

【稲葉光臣】こうした背景には、私たちモビリティランドの社是があります。「人と自然とモビリティを融合し、それを文化として発信すること」。これを体現すべく、一つひとつのアトラクションを設計しています。
――一つひとつのアトラクションにコンセプトを込める。設計にかなりの時間がかかりそうですね。
【稲葉光臣】そうなんです。でも、完成してからお客様の反応を見ると、「あのとき考えたことが伝わってる」と実感できるんです。それがまた意味を持ちはじめるというか、やってよかったなと思える瞬間ですね。
親子で挑戦し、共に育つ場所

――テーマである自然は、季節によって大きく変わりますよね。そうした変化をアトラクションに取り込むことで、春や夏、それぞれの季節に来る意味がより明確になり、リピーターにつながる仕掛けができるかもしれませんね。
【稲葉光臣】まさにおっしゃる通りで、そこはうちの施設ならではの特徴でもあります。ここは自然に囲まれた立地なので、四季の移ろいをはっきりと感じられる。その自然を活かしたコンテンツを、季節ごとにどう練り上げていくかという視点は、とても大事にしています。
――とにかく子どもに優しい取り組みをしている印象があります。そうした企画や子どもたちへの思いを教えてください。
【稲葉光臣】この場所の価値を考えたときに、時代の変化の中で親と子どもの関係性が大きく変わっていると感じています。親の「子どもに何かしてあげたい」という思いは変わっていないはずなのに、現実には公園での自転車練習やボール遊びすら制限される場面が増えている。私自身も、そうした環境で子育てを経験してきました。
【稲葉光臣】とりわけ都市部では、子どもに何かを体験させたいと思っても、環境的にも制度的にも難しいことが多い。結果、親ができることは習い事に頼ることになりがちです。だけど、本来親が子どもと一緒に成長を感じ合えるような体験が、一番大切なはずなんですよね。
【稲葉光臣】ホンダグループが大切にしてきた「挑戦する気持ち」や「成長への意識」といった価値観を、私たちはモビリティを通して表現しています。デジタルが進化する時代にあっても、あえてリアルでしか得られない経験をどう提供していけるか。その意義を日々考えています。
【稲葉光臣】そして、たとえば昔であれば、親子でキャッチボールをして、うっかり頭にボールが当たって泣いてしまうとか、自転車の練習で転んで起き上がる、そんな体験が自然とできていた。でも今はそれすら難しい。だからこそ、我々が持つモビリティというコンテンツや、ここもてぎの自然環境を活かして、親と子どもが一緒に挑戦し、共に成長できる場所をつくっていきたいですね。モビリティや自然といった私たちが持つ要素を掛け合わせて、現代にふさわしい親子の関わり方を提示したいと考えています。

――親子向けのキャンペーンも展開されていますね。
【稲葉光臣】「小学1年生 0円キャンペーン」は、想定以上の反響がありました。もてぎは首都圏から距離があるため、小学1年生を対象にしました。3歳だと長距離移動が大変で、商圏が宇都宮や水戸に限られてしまう。だからこそ、対象年齢を上げて、たとえば埼玉や東京、千葉など首都圏エリアからも来てもらえるように工夫したんです。結果的に、予想を上回る来場があり、私たちとしても驚きました。
【稲葉光臣】そして、「うりんぼサマーパス」も新たにスタートしました。これは、大人1人につき幼児1人のパークパスポートが無料になる仕組みです。ほかのパークでも似た取り組みはありますが、もてぎは本格的な乗り物が多く、幼児が乗れるものが限られる側面もあります。そのため、親子で楽しめる工夫が求められます。親がチケットを買って、さらに子ども分もとなると負担が大きいので、せめてどちらかが買えばもう一方は無料にする。そうすることで、一緒に楽しんでもらえるようにしています。まだまだ改善の余地はありますが、お客様に「これ、お得じゃん」と気づいてもらえる仕組みをこれからも増やしていきたいですね。
――夏ならではの楽しみ方は?
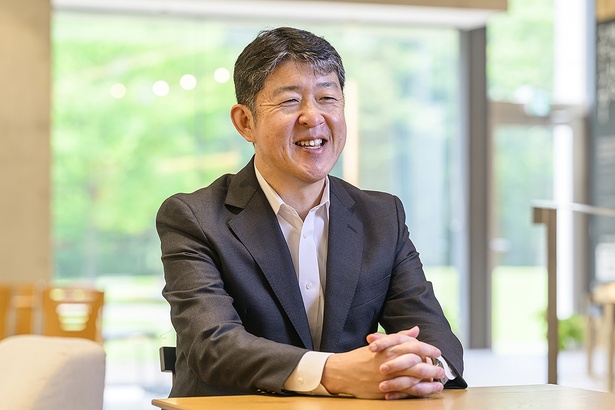
【稲葉光臣】「森のせせらぎ」という小さな子ども向けのじゃぶじゃぶ池を整備しました。これはアトラクションというより、自由に遊んでいただくことができ、水と触れ合いながらクールダウンしていただける場所です。近くには屋内アスレチック「巨大ネットの森 SUMIKA」もあり、この2つを組み合わせることで、夏の暑さをしのぎながら、親子で一日中楽しめる体験ができます。
【稲葉光臣】「巨大ネットの森 SUMIKA」は、全長100メートルもある非常に大きな施設なのですが、これまで十分にその価値を伝えきれていなかった部分もあります。そこで、今期から、「SUMIKA」と同じ建物の中で体験できるもうひとつのアトラクションをアップデート。UNI-ONEというハンズフリーパーソナルモデルに乗りながら、ARの中に広がるもてぎの里山の中に棲む生きものを調査することができます。今後は水場と屋内遊具を組み合わせた夏の過ごし方を、もっとわかりやすく伝えていきたいと思っています。

【稲葉光臣】さらに、涼しい場所として「ホンダコレクションホール」も推しています。堅苦しい印象のある自動車ミュージアムというイメージを払拭し、トミカと連携するなど子どもが入りやすい空間にしていくつもりです。「ホンダコレクションホール」は2024年3月にリニューアルし、ホンダ創業の歴史を「ドラマ」として伝える展示に変わりました。
【稲葉光臣】本田宗一郎と藤澤武夫による挑戦のストーリーを、年表ではなくストーリー性にフォーカスした演出で見せています。この展示はスタートアップ企業の研修にも評価されており、ホンダのスピード感に刺激を受けたという声もいただきます。私たちはこの施設を「気づきの場」として位置づけています。チャレンジや成長は誰かが教えるものではなく、自ら気づくもの。その気づきを促し、支えていくのが私たちの役割だと思っています。そして、その気づきと並列して、グランピングなどの快適な宿泊施設でしっかりと癒やしも提供していく。この「楽しさと学びのバランス」を活かして、企業研修にも活用できる場としての可能性を広げていきたいです。
自然と地域とのつながり

――季節ごとの魅力もありますね。
【稲葉光臣】季節ごとのイベントがそれぞれに特徴的です。たとえばモータースポーツで言えば、秋にはMotoGP、5〜6月にはバイクのトライアル、ほかにもスーパーフォーミュラやGTなどが季節ごとに分散されて開催されています。これらのイベントを通じて、その時期ならではの魅力を感じていただけるようにしています。夏なら夏のイベント、秋にはおいしい食の企画も合わせて展開するなど、自然と一体になった楽しみ方を提案しています。
【稲葉光臣】自然環境そのものも非常に魅力的で、秋から冬にかけては雲海が発生することもありますし、春は周囲の農産物と組み合わせて、いちごなどとのコラボも可能です。夏はホタルが乱舞したり、カブトムシが姿を見せたりと、生き物との出合いも豊富です。こうした自然の魅力を活かしたアクティビティを今後さらに強化していきたいと思っています。
――周辺地域との連携についてはどう考えていますか?
【稲葉光臣】茂木町は、有名な観光地というわけでもなく、アクセスがすごくよいとも言えません。ただ、だからこそ残っている“本物の自然”があると感じています。益子の陶芸や那珂川のヤナ、地元農家の野菜など、この土地に根ざした資源は本当に豊かです。そうした“魅力ある資源”ともっと連携して、地域の価値を伝えていきたいと考えています。
【稲葉光臣】また、私たちが管理する森林では、木の伐採日やCO2の吸収量までモニタリングしています。これは2000年から始めた取り組みで、最近では環境教育の教材としても使えるレベルにまでなっています。生物多様性の観点でも、この地域はとてもユニークです。南の植物と北の植物が交わる場所であり、川でいえばサケとアユが共存できるエリアです。気候帯のちょうど境に位置しているからこその自然の複雑さ、多様さがある。
【稲葉光臣】環境省が進める「生物多様性のための30by30アライアンス」にも2022年4月から参画し、そうした土地の価値をどう“見える化”して伝えていくかを模索しています。きれいなだけの自然ではなく、人と自然が共に生きてきた“里山”の知恵を背景に、こうした多様性や環境の価値を、地域の魅力としてちゃんと形にしていきたいと考えています。
未来に向けた展望と来場者へのメッセージ

――施設として来場者にどのような体験を届けたいと考えていますか?また、イベントや企画を考えるうえで意識していること、大切にしていることは何かを教えてください。
【稲葉光臣】そうですね。子どもにとってのチャレンジ、成長、そしてこの環境への気づき。それが、まず私たちが大切にしていることです。その思いはホテルの客室やグランピングなど、ここ数年で進化してきたサービス全体に込められています。自然の心地よさも含めて、モビリティリゾートもてぎという場所ならではの体験を提供していきたいと考えています。
【稲葉光臣】そして、日本で唯一の二輪モータースポーツの舞台であるMotoGPがあります。金曜日から始まり、日曜日の決勝まで続くあの熱狂と興奮。世界最速のバイクが走るその現場を、この自然環境の中で体験できるのが、モビリティリゾートもてぎならではの魅力です。
【稲葉光臣】でも、ただレースを見るだけではありません。大学時代にバイクに乗っていた仲間と毎年ここで再会する人もいれば、子どもがバイクの免許を取り、親子で再訪する家族もいます。あるいは、思い出の地として再訪してくれる方もいます。そうした人生の節目に、モビリティリゾートもてぎが寄り添える場になっていることが、何よりもうれしいです。
【稲葉光臣】私たちは、レースそのものの価値だけでなく、それを支える環境であるこの里山の自然や空気、空間も含めた価値を育てていきたいと思っています。それが、子どもたちのチャレンジや成長とどう結びつくか、そこまで見据えて取り組んでいきたいですね。
――今後の展望を教えてください。
【稲葉光臣】中でも特に大切だと考えているのが、地域とのアライアンス(連携して関係を構築すること)的な進化です。単に他の観光資源を活用するというより、我々自身が地域に貢献し、そのなかでお互いがWin-Winに成長していけるような関係性をつくる。行政とも連携しながら、枠組みとしてどう整備していくかが、これからの課題だと思っています。

【稲葉光臣】全国的に人口動態が変化していくなかで、我々のような存在が何を担うのか。その意義が問われていると思うんです。だからこそ、新たな取り組みをどんどん進めていかなければならない。
――稲葉さんが考える「理想のレジャー施設像」とはどんなものですか?
【稲葉光臣】理想の施設像について聞かれると、これは本当に難しいんですが、アトラクションやモータースポーツ、里山といった“コンテンツ”単体の話ではないと思っています。親と子、そして未来へとつながる時間軸の中で、この場所が「ここがあってよかった」と思えるような存在であること。それが一番の理想です。
【稲葉光臣】もちろん、ビジネスの視点は大切です。でも、それだけにとらわれるのではなく、10年後、20年後に振り返ったときに存在の意義を実感できるような場所であること。そのためには、今何をすべきか、未来に何を残せるのかを常に考え続ける必要があります。
【稲葉光臣】私たちには、モビリティや自然、子どもたちのチャレンジという強みがあります。これらを通じて、社会課題の解決にも貢献していく。言い換えれば、我々の事業活動そのものがCSV(Creating Shared Value・企業が事業活動を通じて社会的な課題を解決し、経済的な価値と社会的な価値の両方を創造する経営戦略のこと)としての価値を持つような構造にしていきたいんです。
【稲葉光臣】ホンダが製品を通じて社会に貢献しているなら、我々はこの場所を通じて“別のかたちの貢献”を果たす。そんな存在になっていきたいと思っています。
――最後に、来場者へメッセージをお願いします。
【稲葉光臣】モビリティリゾートもてぎでは、世代を問わず誰もが感動できるようなイベントやアトラクションを目指して日々取り組んでいます。花火やMotoGPといった大型イベントはもちろん、親子で一緒に参加することで生まれる「体験としての感動」にもこだわっています。
【稲葉光臣】そして、私たちが持つ自然環境やアトラクションの裏側にある設計思想までをしっかり伝えていきたい。たとえば立体迷路の「迷宮森殿 ITADAKI」もそうですが、まだ伝わりきっていない部分があると感じています。だからこそ、伝える手法や見せ方も含めて磨いていきたいと思っています。
【稲葉光臣】目指したいのは、並んでいるときからワクワクするような演出や、気づいたら心を動かされていたというような体験。そういう仕掛けづくりに、もっと本気で取り組んでいきたいですね。
――ありがとうございました。
広大な自然の中で水と遊び、ネットを駆けのぼり、迷路で頭をひねる。親も夢中になるクラフトや、モビリティの最先端に触れる驚きも待っている。「モビリティリゾートもてぎ」には、ただ遊ぶだけじゃない、学びや気づきがそっと混ざった体験がある。次の休日、親子で“できたね”を重ねる一日を過ごしに、モビリティリゾートもてぎへ出かけてみてはどうだろうか。
この記事の画像一覧(全17枚)
全国アウトドアランキング
アウトドアの楽しみ方
キーワード
- カテゴリ:
- タグ:
- 地域名:
テーマWalker
テーマ別特集をチェック
季節特集
季節を感じる人気のスポットやイベントを紹介
全国約700カ所のイルミネーションを、エリアやカレンダーから探せる完全ガイド!クリスマスマーケット情報も!
全国1400カ所のお花見スポットの人気ランキングから桜祭りや夜桜ライトアップイベントまで、お花見に役立つ情報が満載!
おでかけ特集
今注目のスポットや話題のアクティビティ情報をお届け
キャンプ場、グランピングからBBQ、アスレチックまで!非日常体験を存分に堪能できるアウトドアスポットを紹介